左にやさしい日本語;右にEinfach Deutsch
1. ドイツへの出発
1.1 石炭はもう早くも積み終わった。中くらいの客室のテーブルの周りはとても静かで、電灯のまぶしい光も無意味に感じられる。今夜は、毎晩ここに集まるトランプ仲間もホテルに泊まってしまい、船に残っているのは私一人だけだ。
石炭をば早はや積み果てつ。中等室の卓つくゑのほとりはいと静にて、熾熱燈しねつとうの光の晴れがましきも徒いたづらなり。今宵は夜毎にこゝに集ひ来る骨牌カルタ仲間も「ホテル」に宿りて、舟に残れるは余一人ひとりのみなれば。
1.1 Der Kohletransport ist schon lange beendet. Es ist sehr still um den Tisch im Passagierraum, und das grelle Licht der Lampe ist nutzlos. Heute Abend sind meine Kartenspielpartner, die sich sonst jeden Abend hier versammeln, in einem Hotel, und nur ich allein bin auf dem Schiff geblieben.
1.2 今から五年前のことだった。かねてからの願いが叶い、海外に行くようにという国の命令を受けて、このサイゴンの港まで来た頃は、目にするもの、耳にするもの、すべてが新鮮だった。思うままに書いた紀行文は、毎日何千文字にもなり、当時の新聞に載って世間の人々に人気があった。しかし、今になって考えると、まだ幼い考え、身の程を知らない偉そうな発言、そうでなくても普通の動植物や風景、風俗まで珍しそうに書いた文章を、思慮深い人はどのように見ていたのだろうか。今回は船に乗った時、日記をつけようと買ったノートもまだ白いままだ。これは、ドイツで勉強している間に、どんなものにも感動しない「ニル・アドミラリイ」(※驚くことなかれ)という態度を身につけてしまったのだろうか。いや、これには別の理由がある
五年前いつとせまへの事なりしが、平生ひごろの望足りて、洋行の官命を蒙かうむり、このセイゴンの港まで来こし頃は、目に見るもの、耳に聞くもの、一つとして新あらたならぬはなく、筆に任せて書き記しるしつる紀行文日ごとに幾千言をかなしけむ、当時の新聞に載せられて、世の人にもてはやされしかど、今日けふになりておもへば、穉をさなき思想、身の程ほど知らぬ放言、さらぬも尋常よのつねの動植金石、さては風俗などをさへ珍しげにしるしゝを、心ある人はいかにか見けむ。こたびは途に上りしとき、日記にきものせむとて買ひし冊子さつしもまだ白紙のまゝなるは、独逸ドイツにて物学びせし間まに、一種の「ニル、アドミラリイ」の気象をや養ひ得たりけむ、あらず、これには別に故あり。
1.2 Es war vor fünf Jahren. Mein lange gehegter Wunsch erfüllte sich, und ich erhielt den Regierungsauftrag, ins Ausland zu reisen. Als ich damals im Hafen von Saigon ankam, war alles, was ich sah und hörte, neu für mich. Ich schrieb meine Reiseerinnerungen auf, Tausende von Zeichen pro Tag, und sie wurden in den damaligen Zeitungen veröffentlicht und waren sehr beliebt. Wenn ich heute aber darüber nachdenke, frage ich mich, wie nachdenkliche Menschen meine Texte wohl wahrgenommen haben. Denn es waren unreife Gedanken und überhebliches Gerede. Ich hatte sogar gewöhnliche Tiere, Pflanzen und Bräuche so beschrieben, als wären sie etwas Besonderes. Dieses Mal, als ich an Bord ging, kaufte ich ein Notizbuch, um ein Tagebuch zu schreiben, aber die Seiten sind immer noch leer. Habe ich vielleicht während meines Studiums in Deutschland die Haltung des „Nil admirari“ (sich über nichts wundern) angenommen? Nein, das hat einen anderen Grund.
1.3 確かに、東の国に帰る今の私は、西へ船で向かった昔の私とは違う。学問はまだ満足できていないところも多いが、世の中のつらいことも知った。人の心が頼りにならないのはもちろん、自分自身の心さえ変わりやすいということも悟った。昨日の「正しい」が今日の「間違い」になるような、一瞬一瞬で変わる私の気持ちを、文章にして誰に見せようか。これが日記が書けない理由なのだろうか。いや、これには別の理由がある。
げに東ひんがしに還かへる今の我は、西に航せし昔の我ならず、学問こそ猶なほ心に飽き足らぬところも多かれ、浮世のうきふしをも知りたり、人の心の頼みがたきは言ふも更なり、われとわが心さへ変り易きをも悟り得たり。きのふの是はけふの非なるわが瞬間の感触を、筆に写して誰たれにか見せむ。これや日記の成らぬ縁故なる、あらず、これには別に故あり。
1.3 Tatsächlich bin ich, der jetzt in den Osten zurückkehrt, nicht mehr derselbe, der früher in den Westen reiste. Auch wenn ich in der Wissenschaft noch nicht zufrieden bin, habe ich die Schwierigkeiten des Lebens kennengelernt. Es ist nicht nur so, dass man dem menschlichen Herzen nicht vertrauen kann, sondern ich habe auch erkannt, wie schnell sich mein eigenes Herz ändert. Wer soll meine sich ständig ändernden Gefühle sehen, wo das, was gestern richtig war, heute falsch ist? Ist das der Grund, warum ich kein Tagebuch schreiben kann? Nein, das ist nicht der wahre Grund.
1.4ああ、ブリンディジイの港を出てから、もう二十日以上が経った。普通なら初めて会った人とも交流して、旅の寂しさを慰めあうのが船旅の習慣なのに、少し体調が悪いことを理由に部屋の中にばかりこもって、一緒に旅をする人たちともあまり話をしないのは、誰にも言えない悩みに頭を悩ませているからだ。
嗚呼あゝ、ブリンヂイシイの港を出いでゝより、早や二十日はつかあまりを経ぬ。世の常ならば生面せいめんの客にさへ交まじはりを結びて、旅の憂さを慰めあふが航海の習ならひなるに、微恙びやうにことよせて房へやの裡うちにのみ籠こもりて、同行の人々にも物言ふことの少きは、人知らぬ恨に頭かしらのみ悩ましたればなり。
1.4 Oh, mehr als zwanzig Tage sind vergangen, seit wir den Hafen von Brindisi verlassen haben. Normalerweise ist es üblich auf Seereisen, neue Bekanntschaften zu schließen und sich gegenseitig von der Einsamkeit zu trösten. Aber ich habe mich mit einer leichten Krankheit entschuldigt und bin in meinem Zimmer geblieben. Ich spreche nur wenig mit meinen Mitreisenden, weil mein Herz von einem geheimen Kummer geplagt wird.
1.5この悩みは、最初はほんの一筋の雲のように私の心をかすめ、スイスの美しい山々も見せず、イタリアの古い建物にも感動させなかった。途中からは世の中が嫌になり、自分のことが情けなくなって、毎日腸がねじれるようなつらい痛みを私に与え、今は心の奥底に固まって、一つの影になっている。しかし、手紙を読むたびに、何かを見るたびに、鏡に映る影や、声に呼応する響きのように、限りない昔を懐かしむ気持ちを呼び起こし、何度も私の心を苦しめる。ああ、どうしたらこの悩みを消せるだろうか。もし他の悩みなら、詩を詠んだり歌を歌ったりした後は、気分がすっきりするだろう。これだけはあまりにも深く私の心に刻み込まれているので、そうはいかないだろうと思うが、今夜は周りに誰もいないし、部屋の係が来て電灯のスイッチをひねるまでにはまだ時間もあるだろうから、よし、そのあらましを文章にしてみよう。
此この恨は初め一抹の雲の如く我わが心を掠かすめて、瑞西スヰスの山色をも見せず、伊太利イタリアの古蹟にも心を留めさせず、中頃は世を厭いとひ、身をはかなみて、腸はらわた日ごとに九廻すともいふべき惨痛をわれに負はせ、今は心の奥に凝り固まりて、一点の翳かげとのみなりたれど、文ふみ読むごとに、物見るごとに、鏡に映る影、声に応ずる響の如く、限なき懐旧の情を喚び起して、幾度いくたびとなく我心を苦む。嗚呼、いかにしてか此恨を銷せうせむ。若もし外ほかの恨なりせば、詩に詠じ歌によめる後は心地こゝちすが/\しくもなりなむ。これのみは余りに深く我心に彫ゑりつけられたればさはあらじと思へど、今宵はあたりに人も無し、房奴ばうどの来て電気線の鍵を捩ひねるには猶程もあるべければ、いで、その概略を文に綴りて見む。
1.5 Dieser Kummer schwebte anfangs wie eine einzige Wolke über meinem Herzen, hinderte mich daran, die schönen Berge der Schweiz zu sehen, und ließ mein Herz unberührt von den alten Ruinen Italiens. Später war ich des Lebens überdrüssig und fühlte mich nutzlos. Der Kummer verursachte mir jeden Tag einen Schmerz, der so stark war, als ob sich meine Eingeweide verdrehten. Jetzt hat er sich tief in meinem Herzen festgesetzt und ist zu einem Schatten geworden. Aber jedes Mal, wenn ich einen Brief lese oder etwas sehe, weckt es ein endloses Gefühl der Nostalgie, wie ein Spiegelbild oder ein Echo, und quält mein Herz immer und immer wieder. Oh, wie kann ich diesen Kummer loswerden? Wenn es ein anderer Kummer wäre, würde ich mich vielleicht besser fühlen, nachdem ich ein Gedicht oder ein Lied geschrieben hätte. Aber dieser Kummer ist so tief in mein Herz eingegraben, dass das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Aber heute Abend ist niemand in der Nähe, und es wird noch eine Weile dauern, bis der Zimmermann kommt und das Licht ausschaltet, also werde ich versuchen, eine Zusammenfassung davon zu Papier zu bringen.
1.6 私は幼い頃から厳しい家庭の教えを受けたおかげで、父を早くに亡くしましたが、学業がおろそかになったり衰えたりすることはありませんでした。故郷の藩校にいた時も、東京に出て予備校に通っていた時も、大学の法学部に入った後も、太田豊太郎という私の名前はいつも成績の一番最初に書かれていました。一人っ子の私を頼りに生きてきた母の心も、きっと慰められていたことでしょう。
余は幼き比ころより厳しき庭の訓をしへを受けし甲斐かひに、父をば早く喪うしなひつれど、学問の荒すさみ衰ふることなく、旧藩の学館にありし日も、東京に出でゝ予備黌よびくわうに通ひしときも、大学法学部に入りし後も、太田豊太郎とよたらうといふ名はいつも一級の首はじめにしるされたりしに、一人子ひとりごの我を力になして世を渡る母の心は慰みけらし。
1.6 Ich wurde von klein auf streng erzogen. Obwohl ich meinen Vater früh verlor, wurde mein Studium nicht vernachlässigt. Ob in der Heimat, in Tokio an der Vorschule oder später an der juristischen Fakultät der Universität – der Name Toyotaro Ota stand immer an erster Stelle in der Klasse. Das Herz meiner Mutter, die mich als ihren einzigen Sohn unterstützte, wurde sicherlich getröstet.
1.7 19歳で学士の資格を得て、大学が設立されてからその時までになかったほどの名誉だと人にも言われました。そして、ある省庁に就職し、故郷にいた母を東京に呼び寄せて、楽しい日々を3年ほど過ごしました。上司の覚えも非常にめでたかったので、外国へ行って部署の仕事を調査するようにという命令を受けました。自分の名前を世に出すことも、実家を栄えさせることも、今がその時だと思い、心が勇み立ち、50歳を過ぎた母と別れることもそれほど悲しいとは思いませんでした。そして、遠く離れてベルリンの街へとやって来たのです。
十九の歳には学士の称を受けて、大学の立ちてよりその頃までにまたなき名誉なりと人にも言はれ、某なにがし省に出仕して、故郷なる母を都に呼び迎へ、楽しき年を送ること三とせばかり、官長の覚え殊ことなりしかば、洋行して一課の事務を取り調べよとの命を受け、我名を成さむも、我家を興さむも、今ぞとおもふ心の勇み立ちて、五十を踰こえし母に別るゝをもさまで悲しとは思はず、遙々はる/″\と家を離れてベルリンの都に来ぬ。
1.7 Mit 19 Jahren erhielt ich den Titel eines Bachelors. Man sagte, es sei eine Ehre, die es seit der Gründung der Universität nicht mehr gegeben habe. Ich trat in ein bestimmtes Ministerium ein, holte meine Mutter aus meiner Heimat nach Tokio und verbrachte etwa drei Jahre in glücklicher Zeit. Ich hatte das Vertrauen meiner Vorgesetzten und bekam den Auftrag, ins Ausland zu reisen, um die Arbeit einer Abteilung zu untersuchen. Ich dachte: „Jetzt ist die Zeit gekommen, meinen Namen zu machen und meiner Familie Ruhm zu bringen.” Mein Herz war voller Mut, und ich war nicht besonders traurig, mich von meiner über 50-jährigen Mutter zu verabschieden. So reiste ich weit weg und kam nach Berlin.
1.8 私はあいまいながらも名声を求める気持ちと、勉強する習慣を持って、このヨーロッパの大都市の中心に立った。目を奪うような光や、心を惑わせるような色があふれている。名前だけ聞けば静かな場所のように思える「ウンター・デン・リンデン」という大通りに来ると、両側の石畳には多くの男女が行き交っている。胸を張った軍人、美しく着飾った少女たち、馬車が静かに走り、雲に届くほどの高い建物の間からは、噴水の水が空にきらめいて落ちてくる。遠くにはブランデンブルク門や凱旋塔の女神像が見える。これほど多くの景色が一度に集まっているので、初めて来た者が圧倒されるのは当然だろう。しかし私は、どんなに美しい光景を見ても心を乱されないと誓い、自分を守ろうとしていた。
余は模糊もこたる功名の念と、検束に慣れたる勉強力とを持ちて、忽たちまちこの欧羅巴ヨオロツパの新大都の中央に立てり。何等なんらの光彩ぞ、我目を射むとするは。何等の色沢ぞ、我心を迷はさむとするは。菩提樹下と訳するときは、幽静なる境さかひなるべく思はるれど、この大道髪かみの如きウンテル、デン、リンデンに来て両辺なる石だゝみの人道を行く隊々くみ/″\の士女を見よ。胸張り肩聳そびえたる士官の、まだ維廉ヰルヘルム一世の街に臨める窓に倚より玉ふ頃なりければ、様々の色に飾り成したる礼装をなしたる、妍かほよき少女をとめの巴里パリーまねびの粧よそほひしたる、彼も此も目を驚かさぬはなきに、車道の土瀝青チヤンの上を音もせで走るいろ/\の馬車、雲に聳ゆる楼閣の少しとぎれたる処ところには、晴れたる空に夕立の音を聞かせて漲みなぎり落つる噴井ふきゐの水、遠く望めばブランデンブルク門を隔てゝ緑樹枝をさし交かはしたる中より、半天に浮び出でたる凱旋塔の神女の像、この許多あまたの景物目睫もくせふの間に聚あつまりたれば、始めてこゝに来こしものゝ応接に遑いとまなきも宜うべなり。されど我胸には縦たとひいかなる境に遊びても、あだなる美観に心をば動さじの誓ありて、つねに我を襲ふ外物を遮さへぎり留めたりき。
1.8 Ich hatte den Wunsch nach Ruhm und die Gewohnheit zu lernen, und ich stand nun im Zentrum dieser großen europäischen Stadt. Überall waren Lichter, die die Augen fesselten, und Farben, die das Herz verwirrten. Die Straße „Unter den Linden“ klingt ruhig, aber in Wirklichkeit gehen viele Männer und Frauen auf dem Steinweg an beiden Seiten. Offiziere gingen mit stolz erhobenem Brustkorb, junge Frauen waren schön gekleidet, und Wagen fuhren leise über die Straße. Zwischen den hohen Gebäuden, die fast die Wolken berührten, fiel Wasser aus einem Brunnen glänzend vom Himmel herab. In der Ferne konnte man das Brandenburger Tor und die Statue der Siegesgöttin sehen. So viele Eindrücke zusammen konnten einen Besucher leicht überwältigen. Aber ich schwor mir, dass ich mich von keiner Schönheit verwirren lasse, und ich wollte mein Herz schützen.
1.9 私はベルを鳴らして役人に会い、紹介状を渡してプロイセンに来た理由を伝えた。役人たちは皆、私を快く迎え、もし大使館の手続きが無事に済むなら、何でも教えようと約束してくれた。嬉しかったのは、私が日本の故郷でドイツ語とフランス語を学んでいたことだ。彼らは初めて私に会うと、どこでいつそんなに語学を学んだのかと必ず尋ねた。
余が鈴索すゞなはを引き鳴らして謁えつを通じ、おほやけの紹介状を出だして東来の意を告げし普魯西プロシヤの官員は、皆快く余を迎へ、公使館よりの手つゞきだに事なく済みたらましかば、何事にもあれ、教へもし伝へもせむと約しき。喜ばしきは、わが故里ふるさとにて、独逸、仏蘭西フランスの語を学びしことなり。彼等は始めて余を見しとき、いづくにていつの間にかくは学び得つると問はぬことなかりき。
1.9 Ich klingelte und traf einen Beamten. Ich gab ihm mein Empfehlungsschreiben und erklärte, warum ich nach Preußen gekommen war. Die Beamten empfingen mich freundlich. Sie sagten, wenn die Formalitäten in der Botschaft gut gingen, würden sie mir alles erklären und zeigen.
Ich war froh, dass ich in meiner Heimat Japan Deutsch und Französisch gelernt hatte. Als sie mich zum ersten Mal sahen, fragten sie immer, wo und wann ich diese Sprachen gelernt hatte.
1.10公務の合間には、あらかじめ許可を得てあったので、現地の大学に入学して政治学を学ぶことにし、名簿に名前を記した。
一か月、二か月と過ぎるうちに、公務の打ち合わせも終わり、調査も進んできたので、急ぎのものは報告書にして送り、そうでないものは書き留めてまとめることになった。大学では、思っていたように政治家になるための特別な学科があるわけではなかった。迷いながらも、私は二、三の法律の講義を受けることに決め、授業料を払って通うようになった。
さて官事の暇いとまあるごとに、かねておほやけの許をば得たりければ、ところの大学に入りて政治学を修めむと、名を簿冊ぼさつに記させつ。
ひと月ふた月と過す程に、おほやけの打合せも済みて、取調も次第に捗はかどり行けば、急ぐことをば報告書に作りて送り、さらぬをば写し留めて、つひには幾巻いくまきをかなしけむ。大学のかたにては、穉き心に思ひ計りしが如く、政治家になるべき特科のあるべうもあらず、此か彼かと心迷ひながらも、二三の法家の講筵かうえんに列つらなることにおもひ定めて、謝金を収め、往きて聴きつ。
1.10 In meiner freien Zeit von der Arbeit durfte ich die Universität besuchen.
Ich schrieb meinen Namen in die Liste und wollte dort Staatswissenschaft lernen.
Nach einem oder zwei Monaten waren die Besprechungen in meiner Arbeit beendet, und die Untersuchungen gingen gut voran. Dringende Dinge schrieb ich in Berichte und schickte sie ab. Andere Dinge schrieb ich auf und sammelte sie. An der Universität merkte ich, dass es kein besonderes Fach für zukünftige Politiker gab. Ich war unsicher, aber ich entschied mich, zwei oder drei Vorlesungen im Recht zu hören. Ich zahlte das Geld und ging regelmäßig zu den Vorlesungen.
2. ドイツでの暮らし
2.1 三年ほどの月日は夢のように過ぎていった。けれども、やがて本当の自分の気持ちは隠しきれなくなる。私は父の遺言を守り、母の教えに従い、人から「神童だ」と褒められるのが嬉しくて勉強を怠らずにきた。また、上司に「良い働き手を得た」と励まされるのが嬉しくて、一生懸命に務めてもきた。しかしそのころの私は、ただ言われたことをこなすだけの機械のような人間で、自分で気づくことはなかった。だが二十五歳になり、自由な大学の空気に長く触れたせいか、心の奥に潜んでいた本当の自分が表に現れ、昨日までの自分を責めるようになった。そして私は、自分が政治家になるにも向かず、また法律家になるにもふさわしくないと悟った。
かくて三年ばかりは夢の如くにたちしが、時来れば包みても包みがたきは人の好尚なるらむ、余は父の遺言を守り、母の教に従ひ、人の神童なりなど褒むるが嬉しさに怠らず学びし時より、官長の善き働き手を得たりと奨ますが喜ばしさにたゆみなく勤めし時まで、たゞ所動的、器械的の人物になりて自ら悟らざりしが、今二十五歳になりて、既に久しくこの自由なる大学の風に当りたればにや、心の中なにとなく妥ならず、奥深く潜みたりしまことの我は、やうやう表にあらはれて、きのふまでの我ならぬ我を攻むるに似たり。余は我身の今の世に雄飛すべき政治家になるにも宜しからず、また善く法典を諳じて獄を断ずる法律家になるにもふさはしからざるを悟りたりと思ひぬ。
2.1 Drei Jahre sind wie ein Traum vergangen. Aber irgendwann kann man seine wahren Gefühle nicht mehr verstecken. Ich habe den letzten Wunsch meines Vaters beachtet. Ich habe den Rat meiner Mutter befolgt. Es machte mich glücklich, wenn die Leute mich „Wunderkind“ nannten. Deshalb habe ich immer fleißig gelernt. Es machte mich auch glücklich, wenn mein Chef sagte: „Ich habe einen guten Arbeiter gefunden.“ Deshalb habe ich sehr hart gearbeitet. Aber damals war ich wie eine Maschine, die nur Befehle ausführt. Ich habe das selbst nicht bemerkt. Mit 25 Jahren kam ich an die Universität. Dort habe ich die freie Luft lange gespürt. Deshalb kam mein wahres Ich aus meinem Inneren nach außen. Ich begann, mich selbst von gestern zu kritisieren. Ich erkannte: Ich bin nicht geeignet, Politiker zu werden. Ich erkannte auch: Ich bin nicht passend, Jurist zu werden.
2.2 私はひそかに考えた。母は私を「生きた辞書」にしようとし、上司は私を「生きた法律」にしようとしたのだろう。辞書になるならまだ耐えられる。しかし法律になることは我慢できない。これまで私は小さな問題にも丁寧に答えてきたが、このころから上司に送る文書では「細かい条文にとらわれるべきではない。一度法の精神をつかめば、あとは竹を割るように解決できるはずだ」と大きなことを言うようになった。大学でも法学の授業を避けて、歴史や文学に心を向け、ようやく深く味わって学ぶ段階に入っていった。
余は私に思ふやう、我母は余を活きたる辞書となさんとし、我官長は余を活きたる法律となさんとやしけん。辞書たらむは猶ほ堪ふべけれど、法律たらんは忍ぶべからず。今までは瑣々たる問題にも、極めて丁寧にいらへしつる余が、この頃より官長に寄する書には連りに法制の細目に拘ふべきにあらぬを論じて、一たび法の精神をだに得たらんには、紛々たる万事は破竹の如くなるべしなどゝ広言しつ。又大学にては法科の講筵を余所にして、歴史文学に心を寄せ、漸く蔗を嚼む境に入りぬ。
2.2 Ich dachte heimlich nach. Meine Mutter wollte vielleicht, dass ich ein „lebendes Wörterbuch“ werde. Mein Chef wollte vielleicht, dass ich ein „lebendes Gesetz“ werde. Wörterbuch zu sein, könnte ich noch ertragen. Aber ein Gesetz zu sein, kann ich nicht ertragen. Bisher habe ich auch auf kleine Fragen immer genau geantwortet. Aber in dieser Zeit begann ich, in Briefen an meinen Chef große Dinge zu sagen. Ich schrieb: „Man soll sich nicht zu sehr an kleine Paragrafen binden.“ „Wenn man einmal den Geist des Gesetzes versteht, kann man alles leicht lösen.“ An der Universität mied ich die Vorlesungen in Jura. Stattdessen interessierte ich mich für Geschichte und Literatur. Endlich begann ich, tief zu lernen und wirklich zu genießen.
2.3 しかし上司は、本当は自分の思うままに動かせる機械を作りたかったのだろう。だから独立した考えを持ち、普通ではない態度を示す私を喜ぶはずがない。私の立場は危うくなった。それでも、それだけでは地位を失うほどではなかった。だがベルリンにいた留学生の一部と私との間に好ましくない関係が生まれ、彼らは私を疑い、ついには中傷するようになった。それにも理由があった。
彼らは、私が一緒にビールを飲んだり、玉突き(ビリヤード)をしたりしないのを、頑固さや欲を抑える力のせいだと考え、あざ笑い、ねたんだのだ。しかしそれは、彼らが私を理解していなかったからだ。ああ、そもそも私自身でさえ自分を知らなかったのに、どうして他人に理解できただろうか。
官長はもと心のまゝに用ゐるべき器械をこそ作らんとしたりけめ。独立の思想を懐きて、人なみならぬ面もちしたる男をいかでか喜ぶべき。危きは余が当時の地位なりけり。されどこれのみにては、なほ我地位を覆へすに足らざりけんを、日比伯林の留学生の中にて、或る勢力ある一群と余との間に、面白からぬ関係ありて、彼人々は余を猜疑し、又遂に余を讒誣するに至りぬ。されどこれとても其故なくてやは。
彼人々は余が倶に麦酒の杯をも挙げず、球突きの棒をも取らぬを、かたくななる心と慾を制する力とに帰して、且は嘲り且は嫉みたりけん。されどこは余を知らねばなり。嗚呼、此故よしは、我身だに知らざりしを、怎でか人に知らるべき。
2.3 Mein Chef wollte in Wahrheit wohl eine Maschine machen, die er nach seinem Willen steuern kann. Darum konnte er sich nicht freuen, dass ich eigene Gedanken hatte und ein anderes Verhalten zeigte. Meine Stellung wurde unsicher. Aber nur dadurch hätte ich meine Position noch nicht verloren. Doch zwischen einigen Studenten aus Berlin und mir entstand eine schlechte Beziehung. Sie begannen, mir zu misstrauen. Am Ende fingen sie sogar an, mich schlecht zu machen. Dafür gab es auch einen Grund.
Ich trank kein Bier mit ihnen. Ich spielte auch kein Billard mit ihnen. Sie glaubten, dass komme von meiner Strenge oder von meiner starken Selbstkontrolle. Deshalb lachten sie über mich und waren neidisch. Aber in Wirklichkeit verstanden sie mich nicht. Ach, nicht einmal ich selbst kannte mich richtig. Wie hätten dann die anderen mich verstehen können?
2.4 私の心は「合歓(ねむ)の木の葉」のようで、触れられるとすぐ縮んで避けようとする。私の心は処女のように傷つきやすい。幼いころから年長者の教えを守り、勉学の道を歩み、仕事の道を歩んできたのも、勇気があって優れていたからではなかった。忍耐や努力に見えたものも、実は自分をだまし、人までだましていただけで、人から示された一本道をただたどってきただけだった。心が乱れなかったのも、外のものを捨てて顧みない勇気があったのではなく、ただ外の世界を恐れて自分で自分を縛っていただけだった。
わが心はかの合歓といふ木の葉に似て、物触れば縮みて避けんとす。我心は処女に似たり。余が幼き頃より長者の教を守りて、学の道をたどりしも、仕の道をあゆみしも、皆な勇気ありて能くしたるにあらず、耐忍勉強の力と見えしも、皆な自ら欺き、人をさへ欺きつるにて、人のたどらせたる道を、唯だ一条にたどりしのみ。余所に心の乱れざりしは、外物を棄てゝ顧みぬ程の勇気ありしにあらず、唯外物に恐れて自らわが手足を縛せしのみ。
2.4 Mein Herz ist wie die Blätter des Schlafbaums. Wenn man sie berührt, ziehen sie sich sofort zusammen und wollen weg. Mein Herz ist so empfindlich wie das einer jungen Frau. Schon als Kind habe ich immer den Rat der Älteren befolgt. Ich ging den Weg des Lernens und später den Weg der Arbeit. Aber das war nicht, weil ich mutig oder besonders stark war. Was wie Geduld und Fleiß aussah, war in Wirklichkeit Selbsttäuschung. Ich täuschte auch andere und folgte nur dem klaren Weg, den man mir zeigte. Mein Herz war ruhig, aber nicht aus Mut. Ich hatte nicht den Mut, die äußeren Dinge wegzuwerfen und nicht mehr zu beachten. In Wahrheit hatte ich Angst vor der Außenwelt. Darum habe ich mich selbst gefesselt.
2.5 故郷を出る前、私は自分が立派な人物になることを疑わず、自分の心が耐えられることを信じていた。ああ、しかしそれも一時のこと。船が横浜を離れるまでは、自分を「豪傑」だと思っていたが、実際には涙をこらえきれずハンカチを濡らした。私はそれを不思議に思ったが、これこそが本当の自分だったのだろう。この心は生まれつきのものか、あるいは早く父を亡くして母に育てられたために生じたものか。人々が私をあざ笑ったのは当然かもしれない。だが、私のこの弱く不憫な心を嫉むのは、愚かなことではないだろうか。
故郷を立ちいづる前にも、我が有為の人物なることを疑はず、又我心の能く耐へんことをも深く信じたりき。嗚呼、彼も一時。舟の横浜を離るるまでは、天晴豪傑と思ひし身も、せきあへぬ涙に手巾を濡らしつるを我れ乍ら怪しと思ひしが、これぞなか/\に我本性なりける。此心は生れながらにやありけん、又早く父を失ひて母の手に育てられしによりてや生じけん。
彼人々の嘲るはさることなり。されど嫉むはおろかならずや。この弱くふびんなる心を。
2.5 Bevor ich meine Heimat verließ, zweifelte ich nicht daran, dass ich ein großer Mensch werde. Ich glaubte, dass mein Herz stark genug ist. Ach, aber das war nur für kurze Zeit. Bis das Schiff Yokohama verließ, dachte ich, ich sei ein „Held“. In Wirklichkeit konnte ich meine Tränen nicht zurückhalten. Mein Taschentuch wurde nass. Das fand ich seltsam. Aber vielleicht war das mein wahres Ich. Ist dieses Herz von Geburt an so? Oder kam es daher, dass ich meinen Vater früh verlor und nur von meiner Mutter erzogen wurde? Vielleicht war es natürlich, dass die Leute über mich lachten. Aber mein schwaches und trauriges Herz zu beneiden, ist das nicht dumm?
2.6 カフェには、顔を白と赤に塗って、派手な色の服を着た、お客さんを待っている女性たちがいた。だが、私はその人たちに話しかける勇気がなかった。また、高い帽子をかぶり、鼻に眼鏡をはさんで、ドイツの貴族のような鼻にかかった声で話す「レエベマン」という人とも、遊びに行く勇気がなかった。このような勇気がないため、私は活動的な同郷の人たちと付き合うことができなかった。その結果、彼らは私をからかったり、うらやんだりするだけでなく、私を疑うようになった。このことが、私が無実の罪を背負い、たくさんの苦労をすることになった原因であった。
赤く白く面を塗りて、赫然たる色の衣を纏ひ、珈琲店に坐して客を延く女を見ては、往きてこれに就かん勇気なく、高き帽を戴き、眼鏡に鼻を挾ませて、普魯西にては貴族めきたる鼻音にて物言ふ「レエベマン」を見ては、往きてこれと遊ばん勇気なし。此等の勇気なければ、彼活溌なる同郷の人々と交らんやうもなし。この交際の疎きがために、彼人々は唯余を嘲り、余を嫉むのみならで、又余を猜疑することゝなりぬ。これぞ余が冤罪を身に負ひて、暫時の間に無量の艱難を閲し尽す媒なりける。
2.6 In den Cafés saßen Frauen, die ihre Gesichter weiß und rot geschminkt hatten und auffällige Kleidung trugen. Aber ich hatte nicht den Mut, sie anzusprechen. Auch hatte ich nicht den Mut, mich mit einem Mann namens „Lebemann“ zu amüsieren, der einen hohen Hut trug, eine Brille auf der Nase hatte und mit einem nasalen Ton wie ein deutscher Adliger sprach. Da ich diesen Mut nicht hatte, konnte ich mich nicht mit meinen aktiven Landsleuten treffen. Deswegen haben sie mich nicht nur verspottet und beneidet, sondern sie sind mir auch misstrauisch geworden. Das war der Grund, warum ich unschuldig war, aber so viele Schwierigkeiten hatte.
3. エリスとの出会い
3.1 ある日の夕方、私は動物園のあたりを散歩して、「ウンテル・デン・リンデン」という大通りを通り、モンビシユウ街にある自分のアパートに帰ろうとしていた。そのとき、クロステル横丁の古い教会に着いた。私はたくさんの明かりがある大通りから、この狭くて薄暗い横丁に入ってきた。横丁には、家の二階のベランダに、まだ取り込んでいないシーツや下着が干してある家、長いあごひげを生やしたユダヤ人の老人が家の前に立っている居酒屋などがあった。また、一つのハシゴが二階に、もう一つのハシゴが地下の鍛冶屋の家に通じている貸家もあった。これら300年前の建物は、ひらがなの「へ」の字のように並んで立っていた。この景色を見ると、私はいつもぼんやりして、しばらくその場に立ち止まってしまうのだ。
或る日の夕暮なりしが、余は獣苑を漫歩して、ウンテル、デン、リンデンを過ぎ、我がモンビシユウ街の僑居
に帰らんと、クロステル巷
の古寺の前に来ぬ。余は彼の燈火
の海を渡り来て、この狭く薄暗き巷
に入り、楼上の木欄
に干したる敷布、襦袢
などまだ取入れぬ人家、頬髭長き猶太
教徒の翁
が戸前
に佇
みたる居酒屋、一つの梯
は直ちに楼
に達し、他の梯は窖
住まひの鍛冶
が家に通じたる貸家などに向ひて、凹字
の形に引籠みて立てられたる、此三百年前の遺跡を望む毎に、心の恍惚となりて暫し佇みしこと幾度なるを知らず。
3.1Eines Abends machte ich einen Spaziergang in der Nähe des Zoos, ging durch die große Straße “Unter den Linden” und wollte zu meiner Wohnung in der Monbijoustraße zurückkehren. Zu dieser Zeit kam ich zu einer alten Kirche in der Klosterstraße. Ich kam von der großen Straße mit den vielen Lichtern in diese enge und dunkle Gasse. In der Gasse gab es Häuser, in denen noch Laken und Unterwäsche auf den Balkonen im zweiten Stock hingen, und Kneipen, vor denen alte Juden mit langen Bärten standen. Es gab auch Miethäuser, wo eine Leiter direkt in den zweiten Stock führte und eine andere in das Haus eines Schmieds im Keller. Diese 300 Jahre alten Gebäude standen in der Form des japanischen Zeichens „へ“ in einer Reihe. Wenn ich diese Szenerie sah, wurde ich immer träumerisch und blieb eine Weile stehen.
3.2ちょうどそこを通り過ぎようとしたとき、閉まっている教会の門にもたれて、声を殺して泣いている一人の若い女の子を見つけた。年は16歳か17歳くらいだろう。かぶっている布から少し出ている髪は、うすい金色であった。着ている服は汚れてはいないように見えた。
私の足音に驚いて彼女が振り向いた顔は、言葉ではうまく表現できない。青くてきれいで、何かを訴えているような悲しい目が、少し濡れた長いまつげで半分隠されていた。なぜか、たった一度見ただけで、用心深い私の心の奥深くまでその目が伝わってきたのだ。
今この処を過ぎんとするとき、鎖
したる寺門の扉に倚りて、声を呑みつゝ泣くひとりの少女
あるを見たり。年は十六七なるべし。被
りし巾
を洩れたる髪の色は、薄きこがね色にて、着たる衣は垢つき汚れたりとも見えず。我足音に驚かされてかへりみたる面
、余に詩人の筆なければこれを写すべくもあらず。この青く清らにて物問ひたげに愁
を含める目
の、半ば露を宿せる長き睫毛
に掩
はれたるは、何故に一顧したるのみにて、用心深き我心の底までは徹したるか。
3.2 Gerade als ich vorbeigehen wollte, fand ich ein junges Mädchen, das sich an das geschlossene Kirchentor lehnte und unterdrückt weinte. Sie muss 16 oder 17 Jahre alt gewesen sein. Ihr Haar, das unter ihrem Kopftuch hervorkam, hatte eine hellgoldene Farbe. Ihre Kleidung sah nicht schmutzig aus.
Ihr Gesicht, das sie überrascht von meinen Schritten zu mir drehte, kann ich nicht mit Worten beschreiben. Ihre blauen, klaren und traurigen Augen, die etwas mitteilen wollten, waren halb von ihren langen, leicht feuchten Wimpern bedeckt. Aus irgendeinem Grund drang dieser Blick, den ich nur einmal sah, tief in das Innere meines vorsichtigen Herzens ein.
3.3 彼女は思いがけない深い悲しみに出会って、周りのことなど考える余裕もなく、ここで泣いているのだろうか。私の臆病な心は、かわいそうに思う気持ちに負けてしまった。私は思わず彼女のそばに寄り、「どうして泣いているのだ。私のような関係のない外国人のほうが、かえってあなたを助けやすいこともあるだろう」と話しかけた。自分で言いながら、その大胆さに驚いた。彼女は驚いて、私の黄色い顔をじっと見つめた。私の真剣な気持ちが顔に出ていたのだろう。「あなたはいい人みたいだ。あの人のようにひどくはないだろう。それに、私のお母さんのようにも……。」しばらく止まっていた涙が、またあふれて、かわいらしい頬を流れ落ちた。
彼は料らぬ深き歎きに遭ひて、前後を顧みる遑なく、こゝに立ちて泣くにや。わが臆病なる心は憐憫の情に打ち勝たれて、余は覚えず側に倚り、「何故に泣き玉ふか。ところに繋累なき外人は、却りて力を借し易きこともあらん。」といひ掛けたるが、我ながらわが大胆なるに呆れたり。
彼は驚きてわが黄なる面を打守りしが、我が真率なる心や色に形はれたりけん。「君は善き人なりと見ゆ。彼の如く酷くはあらじ。又た我母の如く。」暫し涸れたる涙の泉は又溢れて愛らしき頬を流れ落つ。
3.3 Traf sie eine unerwartete, tiefe Trauer, sodass sie hier weinte, ohne an ihre Umgebung denken zu können? Mein feiges Herz verlor gegen mein Mitleid. Ich trat unwillkürlich zu ihr und fragte: „Warum weinst du? Ich bin ein Ausländer ohne Verbindung hier, da kann ich dir vielleicht leichter helfen.“ Ich selbst war über meinen Mut überrascht, als ich das sagte. Sie schaute überrascht auf mein gelbes Gesicht. Vielleicht war meine ehrliche Absicht in meinem Gesicht zu sehen. „Du scheinst ein guter Mensch zu sein. Du bist nicht so grausam wie jene Person. Und auch nicht wie meine Mutter…“ Die Tränen, die eine Weile aufgehört hatten, flossen wieder über ihre hübschen Wangen.
3.4 「助けてください。恥をかきたくないんです。母は、私が言うことを聞かなかったので、私を殴りました。父が亡くなったんです。明日、お葬式をしないといけないのに、家には1円もお金がありません」。その後は、泣き声だけが聞こえた。私の目は、うつむいて震えている彼女の首筋にだけ向けられた。「あなたを家に送っていきますから、まず落ち着いてください。そんなに大きな声を出してはいけない。ここは道なのだから」
「我を救ひ玉へ、君。わが恥なき人とならんを。母はわが彼の言葉に従はねばとて、我を打ちき。父は死にたり。明日は葬らではかはぬに、家に一銭の貯だになし。」
跡は欷歔の声のみ。我眼はこのうつむきたる少女の顫ふ項にのみ注がれたり。
「君が家に送り行かんに、先づ心を鎮め玉へ。声をな人に聞かせ玉ひそ。こゝは往来なるに。」彼は物語するうちに、覚えず我肩に倚りしが、この時ふと頭を擡げ、又始てわれを見たるが如く、恥ぢて我側を飛びのきつ。
3.4 Helfen Sie mir. Ich möchte mich nicht schämen. Meine Mutter hat mich geschlagen, weil ich nicht auf sie gehört habe. Mein Vater ist gestorben. Wir müssen morgen eine Beerdigung machen, aber wir haben keinen einzigen Cent zu Hause. Danach hörte ich nur noch ein Weinen. Meine Augen waren nur auf ihren Nacken gerichtet, der gebeugt und zitternd war. “Ich bringe Sie nach Hause, also beruhigen Sie sich zuerst.” “Sie sollen nicht so laut schreien. Wir sind hier auf der Straße.”
3.5 ほかの人に見られるのが嫌で、早足で歩く少女の後についていった。寺の向かいにある大きなドアを入ると、少し壊れた石の階段があった。これを上って、四階まで行くと、腰を曲げて入るような低い戸があった。少女は、さびた針金の先を曲げた取っ手に手をかけて、強く引っ張った。すると、中からせき込むような、かすれた声で「誰だ」と年老いた女性が尋ねた。「エリスが帰りました」と少女が答える間もなく、戸を勢いよく開けたのは、半分白くなった髪の年老いた女性だった。顔つきは悪くなかったが、貧しさの苦労が額にはっきりと刻まれていた。古い毛皮の服を着て、汚れた上履きをはいていた。エリスが私にあいさつしながら家に入ろうとするのを、母親は待てないかのように、戸を勢いよく閉めた。
人の見るが厭はしさに、早足に行く少女の跡に附きて、寺の筋向ひなる大戸を入れば、欠け損じたる石の梯あり。これを上ぼりて、四階目に腰を折りて潜るべき程の戸あり。少女はびたる針金の先きを捩ぢ曲げたるに、手を掛けて強く引きしに、中には咳枯れたる老媼の声して、「誰ぞ」と問ふ。エリス帰りぬと答ふる間もなく、戸をあらゝかに引開けしは、半ば白みたる髪、悪しき相にはあらねど、貧苦の痕を額に印せし面の老媼にて、古き獣綿の衣を着、汚れたる上靴を穿きたり。エリスの余に会釈して入るを、かれは待ち兼ねし如く、戸を劇しくたて切りつ。
3.5 Da sie nicht gesehen werden wollte, ging ich schnell hinter dem Mädchen her. Wir gingen durch eine große Tür gegenüber einem Tempel. Dort war eine Steintreppe, die ein bisschen kaputt war. Wir stiegen hinauf, und im vierten Stock gab es eine niedrige Tür, durch die man sich bücken muss. Das Mädchen fasste den Griff an, der aus einem verbogenen Draht bestand, und zog fest daran. Da fragte eine alte Frau mit einer heiseren, hustenden Stimme von drinnen: “Wer ist da?” Bevor das Mädchen antworten konnte, “Eris ist zurück”, wurde die Tür stark aufgerissen. Es war eine alte Frau mit halb weißem Haar. Ihr Gesicht war nicht böse, aber man sah Spuren von Armut auf ihrer Stirn. Sie trug alte Pelzkleidung und schmutzige Hausschuhe. Als Eris mich begrüßte und eintrat, schloss die Frau die Tür heftig, als ob sie nicht warten könnte.
3.6 私はしばらくの間、ぼんやりと立っていた。ふとランプの光を通して戸を見ると、「エルンスト、ワイゲルト」と書かれていて、その下には「仕立て屋」と書いてあった。これは、さっき亡くなったと少女が言った父親の名前だろう。中では何か言い争うような声が聞こえたが、すぐにまた静かになり、戸が再び開いた。さっきの年老いた女性は、自分の失礼な態度を丁寧に謝って、私を中に招き入れた。戸の内側は台所になっていた。右の低いかまどには、きれいに洗われた白い布がかかっていた。左手には、粗末に積み上げられたレンガのかまどがあった。正面の部屋の戸は半分開いていた。中には白い布で覆われたベッドがあった。寝ているのは亡くなった人だろう。年老いた女性は、かまどの横の戸を開けて私を案内した。
この場所は、いわゆる「屋根裏部屋」で、通りに面した一部屋だったので、天井がなかった。部屋の隅の屋根裏からかまどに向かって斜めに下がっている梁を、紙で覆った下の、立つと頭がぶつかりそうな場所にベッドがあった。真ん中にある机には、美しい毛布がかけられていた。その上には、本が1、2冊と写真集が並んでいて、陶器のつぼには、この場所に似合わない高価な花束が生けられていた。そのそばに少女は恥ずかしそうに立っていた。
余は暫し茫然として立ちたりしが、ふと油燈の光に透して戸を見れば、エルンスト、ワイゲルトと漆もて書き、下に仕立物師と注したり。これすぎぬといふ少女が父の名なるべし。内には言ひ争ふごとき声聞えしが、又静になりて戸は再び明きぬ。さきの老媼は慇懃におのが無礼の振舞せしを詫びて、余を迎へ入れつ。戸の内は厨にて、右手の低きかまどに、真白に洗ひたる麻布を懸けたり。左手には粗末に積上げたる煉瓦の竈あり。正面の一室の戸は半ば開きたるが、内には白布を掩へる臥床あり。伏したるはなき人なるべし。竈の側なる戸を開きて余を導きつ。この処は所謂「マンサルド」の街に面したる一間なれば、天井もなし。隅の屋根裏よりかまどに向ひて斜に下れる梁を、紙にて張りたる下の、立たば頭の支ふべき処に臥床あり。中央なる机には美しき氈を掛けて、上には書物一二巻と写真帖とを列べ、陶瓶にはこゝに似合はしからぬ価高き花束を生けたり。そが傍に少女は羞を帯びて立てり。
3.6 Ich stand eine Weile verwirrt da. Durch das Licht einer Lampe sah ich plötzlich auf die Tür. Darauf stand „Ernst Weigelt“ und darunter „Schneider“. Das muss der Name des Vaters des Mädchens sein, von dem sie gesagt hatte, dass er gestorben ist. Drinnen hörte ich eine Stimme, als ob sie sich stritten. Aber bald wurde es wieder ruhig und die Tür ging noch einmal auf. Die alte Frau entschuldigte sich höflich für ihr unhöfliches Verhalten und bat mich herein. Hinter der Tür war die Küche. Auf der rechten Seite war ein niedriger Ofen mit einem sauberen, weißen Tuch darauf. Auf der linken Seite war ein Ofen aus grob gestapelten Ziegeln. Die Tür zu dem Zimmer gegenüber war halb geöffnet. Drinnen war ein Bett mit einem weißen Tuch bedeckt. Der, der darin lag, musste die verstorbene Person sein. Die alte Frau öffnete die Tür neben dem Ofen und führte mich hindurch.
Dieser Raum war ein Dachzimmer, das auf die Straße blickte, und hatte keine richtige Decke. In einer Ecke, unter einem schrägen Balken vom Dachboden, stand ein Bett. Man musste sich bücken, um dort stehen zu können, ohne den Kopf zu stoßen. Auf dem Tisch in der Mitte lag eine schöne Decke. Darauf lagen ein oder zwei Bücher, ein Fotoalbum und eine Vase aus Keramik. In der Vase stand ein teurer Blumenstrauß, der nicht an diesen Ort passte. Daneben stand das Mädchen, das verlegen aussah.
3.7 彼女はとても美しかった。ミルクのような白い顔が、ランプの光に照らされて、少し赤みを帯びていた。細くてしなやかな手足は、貧しい家の娘たちとは違っていた。年老いた女性が部屋を出て行った後、少女は少しなまった言葉で言った。「どうか、許してください。あなたをこんな場所まで連れてきてしまったことを。あなたは良い人でしょう。私を憎んだりはしないはずです。明日は父の葬式です。頼りにしていたシャウムベルヒさん。あなたは彼を知らないかもしれませんね。彼は『ヴィクトリア座』の役者たちをまとめるリーダーでした。彼に雇われてから、もう2年になるので、きっと私たちを助けてくれると思っていました。しかし、人の苦しい気持ちにつけこんで、わがままな要求をしてくるなんて。どうか、私を助けてください、あなた。お金は、少ないお給料から少しずつ返します。たとえ私がご飯を食べられなくなっても構いません。それが無理なら、母の言う通りに…」彼女は涙を浮かべて、体を震わせた。その見上げた目には、相手に「いやだ」とは言わせないような、魅力があった。この目の使い方は、わざとやっているのか、それとも無意識なのか、分からなかった。
彼は優れて美なり。乳の如き色の顔は燈火に映じて微紅を潮したり。手足の繊くなるは、貧家の女に似ず。老媼の室を出でし跡にて、少女は少し訛りたる言葉にて云ふ。「許し玉へ。君をこゝまで導きし心なさを。君は善き人なるべし。我をばよも憎み玉はじ。明日に迫るは父の葬、たのみに思ひしシヤウムベルヒ、君は彼を知らでやおはさん。彼は「ヰクトリア」座の座頭なり。彼が抱へとなりしより、早や二年なれば、事なく我等を助けんと思ひしに、人の憂に附けこみて、身勝手なるいひ掛けせんとは。我を救ひ玉へ、君。金をば薄き給金を析きて還し参らせん。縦令我身は食はずとも。それもならずば母の言葉に。」彼は涙ぐみて身をふるはせたり。その見上げたる目には、人に否とはいはせぬ媚態あり。この目の働きは知りてするにや、又自らは知らぬにや。
3.7 Sie war sehr schön. Sein Gesicht war weiß wie Milch. Im Licht der Lampe wurde es ein bisschen rot. Seine Hände und Füße waren dünn und weich. Sie waren anders als die der armen Mädchen. Nachdem die alte Frau das Zimmer verlassen hatte, sagte das Mädchen mit leichtem Akzent: „Bitte, verzeih mir. Es tut mir leid, dass ich dich hierher gebracht habe. Du bist sicher ein guter Mensch. Du wirst mich nicht hassen. Morgen ist die Beerdigung meines Vaters. Wir haben auf Herrn Schaumberg gehofft.
Vielleicht kennst du ihn nicht. Er war der Chef des Theaters „Victoria“. Er hat mich vor zwei Jahren angestellt. Deshalb dachte ich, er würde uns helfen. Aber er will unsere Not ausnutzen und stellt egoistische Forderungen. Bitte hilf mir! Ich gebe dir das Geld langsam von meinem kleinen Gehalt zurück. Auch wenn ich dann nichts mehr zu essen habe. Und wenn das nicht geht, dann mache ich, was meine Mutter gesagt hat…“ Er weinte und zitterte. In seinen Augen gab es eine Art Anziehung, die man nicht ablehnen konnte. Ich wusste nicht, ob er das absichtlich tat oder unbewusst.
3.8 私の隠しポケットには、2、3マルクの銀貨はあったが、それでは足りそうになかった。だから、私は時計を外して机の上に置いた。「これで、一時的な困った状況をなんとかしてください。質屋の使いが、モンビシュウ通り3番地に住む太田を探して、そのお金を渡すように伝えてください。」少女は驚いて、感動したようだった。私が別れを言うために差し出した手に、自分の唇を当てた。そして、彼女の熱い涙が、私の手の甲にぽろぽろと落ちた。
我が隠しには二三「マルク」の銀貨あれど、それにて足るべくもあらねば、余は時計をはづして机の上に置きぬ。「これにて一時の急を凌ぎ玉へ。質屋の使のモンビシユウ街三番地にて太田と尋ね来ん折には価を取らすべきに。」
少女は驚き感ぜしさま見えて、余が辞別のために出したる手を唇にあてたるが、はら/\と落つる熱き涙を我手の背に濺ぎつ。
3.8 In meiner Tasche hatte ich zwei oder drei Silbermünzen, aber das schien nicht genug zu sein. Deshalb nahm ich meine Uhr ab und legte sie auf den Tisch. „Damit können Sie eine schwierige Situation überwinden. Sagen Sie dem Boten vom Pfandhaus, er soll Ota in der Rue Montbichou Nummer 3 suchen und ihm das Geld geben.“ Das Mädchen war überrascht und gerührt. Ich streckte meine Hand zum Abschied aus. Sie küsste meine Hand. Und heiße Tränen fielen auf meinen Handrücken.
4. エリスとの交際と、その影響
4.1 ああ、なんて悪い巡り合わせだろう。この恩に感謝するために、自ら私の下宿へやってきた少女は、ショーペンハウエルを右に、シラーを左に置いて、一日中じっと座って読書をする私の書見台のそばで、一輪の美しい花を咲かせた。この時から、私と少女の関係はだんだんと深くなっていった。そして、同じ故郷の日本人にも知られるようになった。彼らはすぐに勘違いして、私が芝居小屋の踊り子を物色している人だと思い込んだ。私たち二人の間には、まだ世間を知らない、幼い楽しみしかなかったのに。
嗚呼、何等の悪因ぞ。この恩を謝せんとて、自ら我僑居に来し少女は、シヨオペンハウエルを右にし、シルレルを左にして、終日兀坐する我読書のに、一輪の名花を咲かせてけり。この時を始として、余と少女との交漸く繁くなりもて行きて、同郷人にさへ知られぬれば、彼等は速了にも、余を以て色を舞姫の群に漁するものとしたり。われ等二人の間にはまだ痴騃なる歓楽のみ存したりしを。
4.1 Ach, was für ein schlechtes Schicksal. Dieses Mädchen kam zu meiner Pension, um sich für meine Hilfe zu bedanken.
Während ich mit Schopenhauer rechts und Schiller links den ganzen Tag still sitze und lese, blühte sie wie eine schöne Blume neben meinem Lesepult. Von diesem Moment an wurde die Beziehung zwischen uns immer enger. Auch meine Landsleute aus Japan erfuhren davon. Sie glaubten schnell falsch, dass ich Frauen suchen würde, die im Nachtleben arbeiten.
Dabei hatten wir zwei doch nur naive, kindliche Freuden.
4.2 その名前を出すことはためらわれるが、同じ故郷の日本人の中に、人のうわさ話が好きな人がいて、私がたびたび芝居小屋に出入りして、踊り子と親しくしているということを、上司のところに報告した。ただでさえ私がひどく学問の道を外れていることを知って、よく思っていなかった上司は、ついに公使館に命令を伝え、私の役人の身分をなくし、仕事を辞めさせた。公使がこの命令を私に伝えた時、こう言った。「もしすぐ故郷に帰るなら、旅費を渡そう。しかし、もしこの場所にまだいるなら、政府の援助を求めることはできない。」私は1週間の猶予をもらい、あれこれと悩んでいるうちに、私の人生で最も悲しい思いをさせた2通の手紙を受け取った。この2通はほとんど同時に送られたものだったが、1通は母が自分で書いた手紙で、もう1通は親戚の誰かが、私が心から慕っていた母の死を知らせる手紙だった。私は母が手紙に書いた言葉を、ここで何度も繰り返すことはできない。涙がこみ上げてきて、ペンを動かすことができなくなるからだ。
その名を斥さんは憚あれど、同郷人の中に事を好む人ありて、余が屡芝居に出入して、女優と交るといふことを、官長の許に報じつ。さらぬだに余が頗る学問の岐路に走るを知りて憎み思ひし官長は、遂に旨を公使館に伝へて、我官を免じ、我職を解いたり。公使がこの命を伝ふる時余に謂ひしは、御身若し即時に郷に帰らば、路用を給すべけれど、若し猶こゝに在らんには、公の助をば仰ぐべからずとのことなりき。余は一週日の猶予を請ひて、とやかうと思ひ煩ふうち、我生涯にて尤も悲痛を覚えさせたる二通の書状に接しぬ。この二通は殆ど同時にいだしゝものなれど、一は母の自筆、一は親族なる某が、母の死を、我がまたなく慕ふ母の死を報じたる書なりき。余は母の書中の言をこゝに反覆するに堪へず、涙の迫り来て筆の運を妨ぐればなり。
4.2 Ich möchte den Namen nicht nennen, aber ein Landsmann von mir, der Gerüchte mochte, berichtete meinem Vorgesetzten, dass ich oft ins Theater gehe und mit einer Tanzerin befreundet sei. Mein Vorgesetzter mochte es schon vorher nicht, dass ich meine Studien vernachlässigte. Schließlich gab er der Botschaft einen Befehl, sodass ich meine Position als Beamter verlor und meinen Job verlassen musste. Als der Botschafter mir diesen Befehl gab, sagte er: „Wenn Sie sofort in Ihre Heimat zurückkehren, geben wir Ihnen die Reisekosten. Aber wenn Sie hier bleiben, können Sie keine Hilfe von der Regierung bekommen.“ Ich bat um eine Woche Aufschub. Während ich darüber nachdachte, bekam ich zwei Briefe, die mir in meinem Leben den größten Schmerz bereiteten. Die beiden Briefe wurden fast gleichzeitig geschickt. Einer war von meiner Mutter selbst. Der andere war von einem Verwandten, der mir den Tod meiner geliebten Mutter mitteilte. Ich kann die Worte, die meine Mutter in dem Brief geschrieben hat, hier nicht wiederholen. Meine Tränen kommen und ich kann den Stift nicht mehr bewegen.
4.3 私とエリスの関係は、この時までは、他の人から見られる以上に清く正しいものでした。彼女は、貧しい父親のために十分な教育を受けることができず、15歳の時に踊りの先生の募集に応じて、この恥ずかしい仕事(踊り子)を教えられました。そして、研修が終わった後、「ヴィクトリア座」に出て、今ではその劇場で二番目の地位を占めるようになっていました。しかし、詩人ハックレンデルが現代の奴隷だと言ったように、踊り子の人生は悲しいものです。わずかな給料で拘束され、昼は練習、夜は舞台と厳しく働かされます。芝居の楽屋に入って初めて、化粧をしたり、美しい衣装を身につけたりすることができます。しかし、舞台の外では、一人分の食事や服にも困ることが多いので、家族を養う者はどれほど苦労するでしょうか。そのため、彼女たちの仲間で、卑しい仕事に落ちぶれない者は、ほとんどいないと言われています。
余とエリスとの交際は、この時までは余所目
に見るより清白なりき。彼は父の貧きがために、充分なる教育を受けず、十五の時舞の師のつのりに応じて、この恥づかしき業
を教へられ、「クルズス」果てゝ後、「ヰクトリア」座に出でゝ、今は場中第二の地位を占めたり。されど詩人ハツクレンデルが当世の奴隷といひし如く、はかなきは舞姫の身の上なり。薄き給金にて繋がれ、昼の温習、夜の舞台と緊
しく使はれ、芝居の化粧部屋に入りてこそ紅粉をも粧ひ、美しき衣をも纏へ、場外にてはひとり身の衣食も足らず勝なれば、親腹からを養ふものはその辛苦奈何
ぞや。されば彼等の仲間にて、賤
しき限りなる業に堕
ちぬは稀
なりとぞいふなる。
4.3 Die Beziehung zwischen Elise und mir war bis dahin reiner und richtiger, als andere Leute es von außen sahen. Wegen ihres armen Vaters konnte sie nicht genug Bildung bekommen. Mit 15 Jahren antwortete sie auf die Anzeige eines Tanzlehrers und lernte diesen schändlichen Beruf als Tänzerin. Nach der Ausbildung ging sie in das Theater „Victoria“ und hatte jetzt dort die zweite Position. Das Leben einer Tänzerin ist traurig. Der Dichter Hackländer sagte, sie seien wie moderne Sklaven. Sie werden mit wenig Geld streng festgehalten und müssen tagsüber üben und nachts auftreten. Erst wenn sie in die Garderobe kommen, können sie sich schminken und schöne Kleider anziehen. Aber außerhalb der Bühne haben sie oft nicht genug Essen oder Kleidung für eine Person. Also müssen diejenigen, die ihre Familie ernähren, große Mühe geben. Man sagt, dass unter ihren Kolleginnen nur wenige nicht auf einen unwürdigen Beruf fallen.
4.4 エリスがこの悲惨な状況を逃れられたのは、彼女の穏やかな性格と、意志の強い父親の保護があったからだった。彼女は幼い頃から、やはり読書が好きだった。しかし、手に入るのは「コルポルタージュ」と呼ばれる、安っぽい貸本屋の小説ばかりだった。私と知り合った頃から、私が貸した本を読んで、次第に読書の面白さを知り、言葉の癖も直り、それほど時が経たないうちに、私に送る手紙の誤字も少なくなっていった。こうして、私たち二人の間には、まず師弟のような関係が生まれたのだった。
私が突然職を失ったことを聞いた時、彼女は顔色を変えた。私は彼女が関わっていることを隠したが、彼女は私に「お母様にはこのことを隠してください」と言った。これは、母が私が学費を失ったことを知って、私を冷遇することを恐れたからだった。
エリスがこれをれしは、おとなしき性質と、剛気ある父の守護とに依りてなり。彼は幼き時より物読むことをば流石に好みしかど、手に入るは卑しき「コルポルタアジユ」と唱ふる貸本屋の小説のみなりしを、余と相識る頃より、余が借しつる書を読みならひて、漸く趣味をも知り、言葉の訛をも正し、いくほどもなく余に寄するふみにも誤字少なくなりぬ。かゝれば余等二人の間には先づ師弟の交りを生じたるなりき。我が不時の免官を聞きしときに、彼は色を失ひつ。余は彼が身の事に関りしを包み隠しぬれど、彼は余に向ひて母にはこれを秘め玉へと云ひぬ。こは母の余が学資を失ひしを知りて余を疎んぜんを恐れてなり。
4.4 Elise konnte dieser elenden Situation entkommen, denn es lag an ihrem sanften Charakter und am Schutz ihres willensstarken Vaters. Schon als kleines Kind mochte sie das Lesen. Aber sie konnte nur billige Romane aus der Leihbibliothek bekommen, die man „Kolportage“ nannte. Als sie mich kennenlernte, las sie die Bücher, die ich ihr gab, wodurch sie langsam lernte, wie interessant das Lesen ist. Dadurch verbesserten sich ihre Sprachfehler, und sie machte nach kurzer Zeit weniger Rechtschreibfehler in ihren Briefen an mich. So entstand zuerst eine Lehrer-Schüler-Beziehung zwischen uns beiden.
Als sie hörte, dass ich plötzlich meinen Job verloren hatte, wurde sie blass. Ich versteckte, dass sie etwas damit zu tun hatte. Aber sie sagte zu mir: „Bitte verheimlichen Sie das meiner Mutter.“ Sie hatte Angst, dass meine Mutter mich schlecht behandeln würde, wenn sie wüsste, dass ich mein Studienhonorar verloren hatte.
ああ、細かいことはここに詳しく書く必要はない。私が彼女を愛する気持ちが急に強くなり、ついに離れられない仲になったのは、この時だった。自分の人生の一大事が目の前にあり、まさに生きるか死ぬかという危機的な状況なのに、このような行動(エリスと深く結ばれること)をとったことを、おかしいと思う人や、非難する人もいるだろう。しかし、私がエリスを愛する気持ちは、初めて会った時から決して浅くはなかったし、その上、私の不運を憐れんで、別れを悲しんでうつむいている彼女の顔に、乱れた髪がかかっている、その美しくて健気(けなげ)な姿が、私の深い悲しみと感情の波によって、普段とは違う状態になっていた私の心(脳髄)を突き動かして、私は我を忘れたような(恍惚とした)状態になって、このような関係になってしまったことに、何ができただろうか。私にはどうすることもできなかった。
嗚呼、委
くこゝに写さんも要なけれど、余が彼を愛
づる心の俄
に強くなりて、遂に離れ難き中となりしは此折なりき。我一身の大事は前に横
りて、洵
に危急存亡の秋
なるに、この行
ありしをあやしみ、又た誹
る人もあるべけれど、余がエリスを愛する情は、始めて相見し時よりあさくはあらぬに、いま我数奇
を憐み、又別離を悲みて伏し沈みたる面に、鬢
の毛の解けてかゝりたる、その美しき、いぢらしき姿は、余が悲痛感慨の刺激によりて常ならずなりたる脳髄を射て、恍惚の間にこゝに及びしを奈何
にせむ。
Ach, ich muss die Details hier nicht genau aufschreiben. Zu diesem Zeitpunkt wurde meine Liebe zu Elise plötzlich sehr stark. Wir wurden ein Paar, das sich nicht mehr trennen konnte. Ich stand vor einer großen, gefährlichen Sache in meinem Leben. Es war eine Frage von Leben und Tod. Trotzdem tat ich das. Manche Leute werden das seltsam finden oder mich dafür kritisieren. Meine Liebe zu Elise war aber nicht klein, schon als wir uns das erste Mal trafen. Jetzt sah sie mein Unglück und war traurig wegen der Trennung. Ihre Haare hingen auf ihr schönes, gesenktes Gesicht. Diese schöne und tapfere Erscheinung traf mein Gehirn. Mein Kopf war wegen meiner tiefen Trauer und meiner starken Gefühle in einem ungewöhnlichen Zustand. Ich war in diesem Moment wie betäubt und kam so zu dieser tiefen Beziehung.Was konnte ich tun?
公使と約束した日も近づき、私の運命が迫ってきた。もしこのまま故郷に帰っても、学問を修められず、汚名を負った私の身が浮かび上がる機会はないだろう。しかし、だからといってベルリンに留まることにしても、学費を得る方法がなかった。この時、私を助けてくれたのは、今の私の同僚の一人である相沢謙吉だった。彼は東京におり、すでに天方伯(あまかたはく)の秘書官になっていたが、私がクビになったことが官報に出ているのを見て、ある新聞社の編集長に話を持ちかけた。そして、私をその会社の通信員にして、ベルリンに留まらせ、政治や学問の出来事などを報道させるように手配してくれたのだった。
公使に約せし日も近づき、我命はせまりぬ。このまゝにて郷にかへらば、学成らずして汚名を負ひたる身の浮ぶ瀬あらじ。さればとて留まらんには、学資を得べき手だてなし。
此時余を助けしは今我同行の一人なる相沢謙吉なり。彼は東京に在りて、既に天方伯の秘書官たりしが、余が免官の官報に出でしを見て、某新聞紙の編輯長に説きて、余を社の通信員となし、伯林に留まりて政治学芸の事などを報道せしむることとなしつ。
Der Tag, den ich dem Gesandten versprochen hatte, kam näher. Mein Schicksal wurde dringend. Wenn ich so in meine Heimat zurückkehrte, hätte ich keine Chance, wieder Ansehen zu gewinnen. Ich hatte meine Studien nicht beendet und Schande auf mich geladen. Aber wenn ich in Berlin bleiben wollte, hatte ich keine Möglichkeit, mein Studienhonorar zu bekommen. In dieser Zeit half mir Kenkichi Aizawa, der heute einer meiner Kollegen ist. Er war in Japan (Tokio) und war schon der Sekretär von Graf Amakata. Er sah im Amtsblatt, dass ich entlassen worden war (meine Entlassung). Deshalb sprach er mit dem Chefredakteur einer Zeitung. Und er sorgte dafür, dass ich als Korrespondent für seine Firma in Berlin bleiben konnte. Dort sollte ich über Politik und wissenschaftliche Themen berichten.
新聞社の報酬は取るに足らないほど少なかった。しかし、住むところを変えて、昼食をとる店も変えたりすれば、つつましい生活は送れるだろう。あれこれと考えているうちに、心の誠意を示して私に助けの手を差し伸べたのはエリスだった。彼女がどのように母親を説得したのかわからないが、私は彼女たち親子の家に身を寄せることになった。こうして、エリスと私は、いつからか、わずかな収入を合わせて、苦しい中でも楽しい日々を送ることになった。
社の報酬はいふに足らぬほどなれど、棲家
をもうつし、午餐
に往く食店
をもかへたらんには、微
なる暮しは立つべし。兎角
思案する程に、心の誠を顕
はして、助の綱をわれに投げ掛けしはエリスなりき。かれはいかに母を説き動かしけん、余は彼等親子の家に寄寓することゝなり、エリスと余とはいつよりとはなしに、有るか無きかの収入を合せて、憂きがなかにも楽しき月日を送りぬ。
Die Bezahlung von der Zeitung war sehr gering. Aber wenn ich umzog und auch das Restaurant für das Mittagessen wechselte, dann würde ein bescheidenes Leben möglich sein. Während ich darüber nachdachte, zeigte Elise ihre ehrliche Absicht und bot mir Hilfe an. Ich weiß nicht, wie sie ihre Mutter überredet hatte. Aber ich konnte bei der Familie wohnen. Elise und ich legten unmerklich unser geringes Einkommen zusammen und verbrachten so auch in schweren Zeiten fröhliche Tage
朝のコーヒーを飲み終わると、エリスは学校へ行った。学校へ行かない日は、家にいた。私は、キヨオニヒ通りにある、入り口が狭くて奥だけが長い休憩所へ行った。そこで全部の新聞を読み、鉛筆を出して、色々な情報を集めた。この、窓から光が入る部屋で、私は他の客と隣り合って座った。他の客は、決まった仕事がない若者や、少ないお金を人に貸して遊んで暮らす老人、仕事の合間に休んでいる商人などだった。
私は冷たい石のテーブルの上で、忙しそうにペンを走らせた。店員が持ってくるコーヒーが冷めるのも気にしなかった。たくさんの種類の新聞が細長い棒に挟んで壁にかけられていたが、その横を何度も行ったり来たりする私を、知らない人はどう見ていたのだろうか。また、昼の一時ごろになると、エリスが学校に行った日は、帰りにこの店に寄った。そして、私と一緒に店を出る、非常に身のこなしが軽い、手のひらの上で舞うこともできそうな少女を見て、不思議に思って見送る人もいたに違いない。
朝の珈琲果つれば、彼は温習に往き、さらぬ日には家に留まりて、余はキヨオニヒ街の間口せまく奥行のみいと長き休息所に赴き、あらゆる新聞を読み、鉛筆取り出でゝ彼此と材料を集む。この截り開きたる引竈より光を取れる室にて、定りたる業なき若人、多くもあらぬ金を人に借して己れは遊び暮す老人、取引所の業の隙を偸みて足を休むる商人などと臂を並べ、冷なる石卓の上にて、忙はしげに筆を走らせ、小をんなが持て来る一盞の珈琲の冷むるをも顧みず、明きたる新聞の細長き板ぎれに挿みたるを、幾種となく掛け聯ねたるかたへの壁に、いく度となく往来する日本人を、知らぬ人は何とか見けん。又一時近くなるほどに、温習に往きたる日には返り路によぎりて、余と倶に店を立出づるこの常ならず軽き、掌上の舞をもなしえつべき少女を、怪み見送る人もありしなるべし。
Nachdem der Morgenkaffee getrunken war, ging Ellis zur Schule. An den Tagen, an denen sie nicht zur Schule ging, blieb sie zu Hause. Ich ging in ein Rastlokal in der Königstraße, das einen schmalen Eingang, aber einen sehr langen Raum hatte. Dort las ich alle Zeitungen und sammelte verschiedene Informationen mit meinem Bleistift. In diesem Zimmer, das Licht durch das Fenster bekam, saß ich neben den anderen Gästen. Die anderen Gäste waren junge Leute ohne feste Arbeit, ältere Männer, die wenig Geld verliehen und damit ihr Leben verbrachten, sowie Kaufleute, die sich in der Pause von ihrer Arbeit erholten.
Ich schrieb auf dem kalten Steintisch eifrig mit dem Stift. Es war mir egal, dass der Kaffee, den die Bedienung brachte, kalt wurde. Die verschiedenen Zeitungen hingen auf Stangen an der Wand. Was dachten wohl die Fremden über mich, den Japaner, der immer wieder an dieser Wand auf und ab ging? Gegen eins Uhr mittags kam Ellis an den Tagen, an denen sie in der Schule gewesen war, auf dem Rückweg in dieses Lokal. Es gab sicher auch Leute, die uns verwundert nachsahen, als Ellis und ich das Lokal zusammen verließen – dieses Mädchen, das extrem leichtfüßig war und sogar auf einer Handfläche tanzen könnte.
私の勉強は、おろそかになってしまった。屋根裏部屋にある小さな明かり(ランプ)が、かろうじて燃えている。エリスが劇場から帰ってきて、椅子に座って裁縫(さいほう)などをする、そのすぐそばの机で、私は新聞の原稿を書いていた。以前は、古い法律や規則といった「枯れた葉」のようなつまらないテーマを紙の上に集めて書いていたのとは、まったく違う。今は、活発な政治の世界の動きや、文学・美術に関する新しい出来事の批評など、色々なものを関連づけて書いた。ビョルンソンという作家から学ぶよりは、むしろハイネという作家から表現を学んで考えをまとめ、できる限りの力を尽くし、様々な文章を書いた。その中でも、特に、ヴィルヘルム一世とフリードリヒ三世という二人の皇帝の死(崩殂)が立て続けにあったことや、新しい皇帝の即位、そしてビスマルク侯爵の今後がどうなるか、といった政治的な出来事については、特に詳しく報告した。そのため、この頃からは思っていた以上に忙しくなり、持っている数少ない本を開いて読んだり、昔の勉強をしたりする時間もほとんど取れなくなった。大学の学籍(がくせき)はまだ残されていたが、授業料を払うのが難しくなったので、唯一残しておいた授業でさえ、聞きに行くことは滅多になくなった。
我学問は荒みぬ。屋根裏の一燈微に燃えて、エリスが劇場よりかへりて、椅に寄りて縫ものなどする側の机にて、余は新聞の原稿を書けり。昔しの法令条目の枯葉を紙上に掻寄せしとは殊にて、今は活溌々たる政界の運動、文学美術に係る新現象の批評など、彼此と結びあはせて、力の及ばん限り、ビヨルネよりは寧ろハイネを学びて思を構へ、様々の文を作りし中にも、引続きて維廉一世と仏得力三世との崩殂ありて、新帝の即位、ビスマルク侯の進退如何などの事に就ては、故らに詳かなる報告をなしき。さればこの頃よりは思ひしよりも忙はしくして、多くもあらぬ蔵書を繙き、旧業をたづぬることも難く、大学の籍はまだ刪られねど、謝金を収むることの難ければ、唯だ一つにしたる講筵だに往きて聴くことは稀なりき。
Meine Studien wurden vernachlässigt. Eine kleine Lampe auf dem Dachboden brannte nur schwach. An einem Tisch neben dem Stuhl, auf dem Elis saß und nähte, nachdem sie aus dem Theater zurückgekehrt war, schrieb ich Zeitungsartikel. Das war völlig anders, als früher langweilige Themen wie alte Gesetze und Regeln, die wie „dürre Blätter“ waren, auf Papier zu sammeln. Jetzt verband ich verschiedene Dinge, wie die aktiven Bewegungen in der politischen Welt und Kritiken über neue Phänomene in Literatur und Kunst. Ich gab mein Bestes und strukturierte meine Gedanken, indem ich eher vom Dichter Heine als vom Autor Bjørnson lernte, und verfasste verschiedene Texte. Insbesondere über die aufeinanderfolgenden Tode der beiden Kaiser Wilhelm I. und Friedrich III., die Thronbesteigung des neuen Kaisers und die Frage nach dem Verbleib des Fürsten Bismarck berichtete ich besonders detailliert. Deshalb war ich ab dieser Zeit beschäftigter, als ich gedacht hatte, und es wurde schwierig, die wenigen Bücher, die ich besaß, aufzuschlagen oder mich meinen früheren Studien zu widmen. Meine Immatrikulation an der Universität war zwar noch nicht gelöscht, aber da es schwer war, die Studiengebühren zu bezahlen, ging ich selbst zur einzigen noch belegten Vorlesung nur noch selten hin.
私は、専門の勉強をあまりしなくなった。しかし、それとは別の特別な知識を身につけた。その知識について説明する。一般の人々の間で学問が広がっているのは、ヨーロッパの国々の中でドイツが一番だろう。たくさんの新聞や雑誌に出ている議論には、とてもレベルが高いものが多い。私は通信員になったときから、昔、大学に熱心に通って得た、物事を見抜く力を使って、その記事を何度も読んだり、書き写したりした。そのおかげで、今まで一つの道だけを学んでいた私の知識は、自然と全体をまとめたものになった。そして、同じ国から来ている留学生のほとんどが知らない世界にたどり着いた。彼らの仲間には、ドイツの新聞の社説さえも、きちんと読めない人がいるのだから。
我学問は荒みぬ。されど余は別に一種の見識を長じき。そをいかにといふに、凡
そ民間学の流布
したることは、欧洲諸国の間にて独逸に若
くはなからん。幾百種の新聞雑誌に散見する議論には頗
る高尚なるもの多きを、余は通信員となりし日より、曾
て大学に繁く通ひし折、養ひ得たる一隻の眼孔もて、読みては又読み、写しては又写す程に、今まで一筋の道をのみ走りし知識は、自
ら綜括的になりて、同郷の留学生などの大かたは、夢にも知らぬ境地に到りぬ。彼等の仲間には独逸新聞の社説をだに善くはえ読まぬがあるに。
Mein Fachstudium habe ich vernachlässigt. Dennoch habe ich mir eine andere, besondere Art von Wissen angeeignet. Dieses Wissen werde ich nun erklären. Was die Verbreitung von wissenschaftlichem Denken unter der Bevölkerung angeht, so ist Deutschland unter den europäischen Ländern wohl die Nummer eins. In den Diskussionen in zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften gibt es viele sehr anspruchsvolle Inhalte. Seit ich Korrespondent wurde, habe ich mithilfe meiner Urteilsfähigkeit, die ich mir damals durch den eifrigen Besuch der Universität erwarb, die Artikel immer wieder gelesen und abgeschrieben. Dadurch wurde mein Wissen, das zuvor nur einem einzigen Bereich galt, von selbst umfassender. So erreichte ich einen Zustand, den die meisten Kommilitonen aus meinem Heimatland nicht einmal erträumen. Unter ihnen gibt es nämlich Leute, die nicht einmal die Leitartikel der deutschen Zeitungen richtig lesen können.
明治21年(1888年)の冬がやって来た。表通りの歩道では、滑らないように砂をまいたり、(農具の)鋤を使って氷を割ったりしている。クロステル通りのあたりは、道がデコボコで歩きにくそうな場所も見える。しかし、家の前は一面凍っていて、朝にドアを開けると、お腹をすかせて凍え死んだスズメが落ちて死んでいるのが見え、かわいそうになった。部屋を温め、ストーブに火をつけても、石の壁を突き抜け、服の綿まで通り抜ける北ヨーロッパの寒さは、とても我慢できないものだった。エリスは二、三日前の夜、舞台で倒れて、人に助けられて帰ってきた。それからずっと気分が悪いと言って休み、何か食べるたびに吐くのを見て、「これは(妊娠初期の)つわりではないか」と初めて気がついたのは彼女の母だった。ああ、ただでさえ自分の将来がどうなるか不安なのに、もし本当に(妊娠が)事実だとしたら、私はどうすればいいのだろうか。
明治廿一年の冬は来にけり。表街の人道にてこそ沙をも蒔け、鋤をも揮へ、クロステル街のあたりは凸凹坎坷の処は見ゆめれど、表のみは一面に氷りて、朝に戸を開けば飢ゑ凍えし雀の落ちて死にたるも哀れなり。室を温め、竈に火を焚きつけても、壁の石を徹し、衣の綿を穿つ北欧羅巴の寒さは、なか/\に堪へがたかり。エリスは二三日前の夜、舞台にて卒倒しつとて、人に扶けられて帰り来しが、それより心地あしとて休み、もの食ふごとに吐くを、悪阻といふものならんと始めて心づきしは母なりき。嗚呼、さらぬだに覚束なきは我身の行末なるに、若し真なりせばいかにせまし。
Es war der Winter des Jahres 1888 gekommen. Auf den Gehwegen der Hauptstraße streute man Sand aus, damit niemand ausrutschte, und man hackte das Eis mit einem Pflug auf. Die Wege in der Klosterstraße wirkten uneben und schwer begehbare. Aber nur der Boden vor unserer Wohnung war völlig vereist. Als ich an diesem Morgen die Tür öffnete, sah ich einen verhungerten und erfrorenen Spatz tot auf dem Boden liegen, was sehr traurig war. Obwohl wir das Zimmer heizten und im Ofen Feuer machten, war die Kälte Nordeuropas unerträglich, denn sie drang durch die Steinwände und sogar durch die Watte unserer Kleidung. Elis war vor zwei oder drei Nächten auf der Bühne ohnmächtig geworden und wurde von Leuten gestützt nach Hause gebracht. Seitdem blieb sie zu Hause, weil ihr übel war, und ihre Mutter bemerkte zuerst: „Das könnte Schwangerschaftsübelkeit sein“, weil Elis jedes Mal erbrach, wenn sie etwas aß. Ach, meine eigene Zukunft war ohnehin schon ungewiss und voller Sorgen. Was sollte ich nur tun, wenn es tatsächlich wahr wäre?
今朝は日曜日なので家にいたが、気分は晴れなかった。
エリスは寝こむほどではないが、小さな鉄のストーブのそばに椅子を寄せて、ほとんど話さなかった。
そのとき、戸口のほうで人の声がした。まもなく台所にいたエリスの母が、郵便の手紙を持ってきて私に渡した。見ると、見覚えのある相沢の字で書かれており、切手はプロイセンのもので、消印にはベルリンとあった。私は不思議に思いながら手紙を開き、読んだ。そこにはこう書いてあった。――「急なことで前もって知らせられなかったが、昨夜、天方大臣のお供で私もここに来た。大臣が君に会いたいとおっしゃっている。すぐ来てほしい。君の名誉を取り戻すのは今しかない。急いでこの知らせだけ伝える。」読み終えた私のぼんやりした顔を見て、エリスが言った。「故郷からの手紙ですか。悪い知らせではないでしょう。」彼女は、いつもの新聞社の報酬に関する手紙だと思ったのだろう。
「いや、違う。心配しなくていい。君も知っている相沢が、大臣と一緒にここに来て、私を呼んでいる。急げというのだから、すぐに行かねばならない。」
今朝は日曜なれば家に在れど、心は楽しからず。エリスは床に臥
すほどにはあらねど、小
き鉄炉の畔
に椅子さし寄せて言葉寡
し。この時戸口に人の声して、程なく庖厨
にありしエリスが母は、郵便の書状を持て来て余にわたしつ。見れば見覚えある相沢が手なるに、郵便切手は普魯西
のものにて、消印には伯林
とあり。訝
りつゝも披
きて読めば、とみの事にて預
め知らするに由なかりしが、昨夜
こゝに着せられし天方大臣に附きてわれも来たり。伯の汝
を見まほしとのたまふに疾
く来よ。汝が名誉を恢復するも此時にあるべきぞ。心のみ急がれて用事をのみいひ遣
るとなり。読み畢
りて茫然たる面もちを見て、エリス云ふ。「故郷よりの文なりや。悪しき便
にてはよも。」彼は例の新聞社の報酬に関する書状と思ひしならん。「否、心にな掛けそ。おん身も名を知る相沢が、大臣と倶にこゝに来てわれを呼ぶなり。急ぐといへば今よりこそ。」
Heute ist Sonntag, deshalb blieb ich zu Hause. Aber meine Stimmung war nicht gut. Ellis war nicht krank im Bett, aber sie saß still neben dem kleinen Eisenofen. Sie sprach fast nichts. In diesem Moment hörte ich eine Stimme an der Tür. Bald kam Ellis’ Mutter aus der Küche und brachte mir einen Brief. Ich sah die Schrift und erkannte, dass sie von Aizawa war. Die Briefmarke war aus Preußen, und der Stempel sagte „Berlin“. Ich wunderte mich, öffnete aber den Brief und las ihn. Darin stand: „Wegen einer plötzlichen Angelegenheit konnte ich dir vorher nichts sagen, aber ich bin gestern Abend mit Minister Amakata hier angekommen. Der Minister will dich sehen. Komm schnell! Jetzt ist die Zeit, deinen guten Namen zurückzubekommen.“ Nachdem ich den Brief gelesen hatte, sah Ellis mein nachdenkliches Gesicht. Sie sagte: „Ist es ein Brief aus deiner Heimat? Es ist sicher keine schlechte Nachricht.“ Sie dachte wohl, es sei ein Brief über das Geld von der Zeitung. Ich sagte: „Nein, mach dir keine Sorgen. Aizawa, den du kennst, ist mit dem Minister hier und ruft mich. Er sagt, ich soll schnell kommen, also muss ich jetzt gehen.“
「何が富や名誉だ。」と私は微笑んだ。「政治の世界に出ようという望みを捨ててから、もう何年もたった。大臣の顔など見たくもない。ただ、長いあいだ会っていなかった友に会いに行くだけだ。」エリスの母が呼んだ一等馬車「ドロシェ」は、雪の道を車輪をきしませながら窓の下まで来た。私は手袋をはめ、少し汚れた外套を肩にかけ、帽子を取ってエリスに口づけし、階上から下へ降りた。彼女は凍った窓を開け、乱れた髪を北風に吹かせながら、私の乗った馬車を見送った。
「何、富貴。」余は微笑しつ。「政治社会などに出でんの望みは絶ちしより幾年をか経ぬるを。大臣は見たくもなし。唯年久しく別れたりし友にこそ逢ひには行け。」エリスが母の呼びし一等「ドロシユケ」は、輪下にきしる雪道を窻の下まで来ぬ。余は手袋をはめ、少し汚れたる外套を背に被ひて手をば通さず帽を取りてエリスに接吻して楼を下りつ。彼は凍れる窻を明け、乱れし髪を朔風に吹かせて余が乗りし車を見送りぬ。
„Was sind Reichtum und Ehre?“ sagte ich lächelnd. „Seit ich den Wunsch aufgegeben habe, in die Politik zu gehen, sind viele Jahre vergangen.“ „Ich möchte keinen Minister mehr sehen.“ „Ich will nur einen alten Freund besuchen, den ich lange nicht gesehen habe.“ Der Wagen, den Ellis’ Mutter gerufen hatte, kam unter das Fenster. Es war eine gute Kutsche mit starken Pferden. Ich zog meine Handschuhe an, nahm meinen etwas schmutzigen Mantel und setzte meinen Hut auf. Dann küsste ich Ellis und ging die Treppe hinunter. Sie öffnete das gefrorene Fenster und sah mir nach. Der kalte Nordwind spielte mit ihrem Haar.
私が車を降りたのは「カイゼルホオフ」の入り口だ。門番に、秘書官の相沢がいる部屋の番号を聞いた。久しぶりに踏み慣れない大理石の階段を上り、中央の柱に布をかぶせたソファーがあり、正面に鏡が置いてある応接室に入った。ここでコートを脱ぎ、廊下を通って部屋の前まで行ったが、私は少しためらった。同じ大学にいた時、私の行いが正しいことをほめてくれた相沢が、今日はどんな顔で私を迎えるだろうか。部屋に入って向かい合ってみると、相沢は前よりも体が太く、がっしりとしていたが、以前と変わらず明るい性格で、私が失敗したことなど、あまり気にしていないようだった。別れてからのことを詳しく話す時間もなく、相沢に連れられて大臣に会いに行った。大臣から頼まれたのは、ドイツ語で書かれた、急ぎの文書を翻訳することだった。私が文書を受け取って大臣の部屋を出た時、相沢が後から来て、私と昼ごはんを一緒に食べようと言ったのだ。
余が車を下りしは「カイゼルホオフ」の入口なり。門者に秘書官相沢が室の番号を問ひて、久しく踏み慣れぬ大理石の階を登り、中央の柱に「プリユツシユ」を被へる「ゾフア」を据ゑつけ、正面には鏡を立てたる前房に入りぬ。外套をばこゝにて脱ぎ、廊をつたひて室の前まで往きしが、余は少し踟蹰したり。同じく大学に在りし日に、余が品行の方正なるを激賞したる相沢が、けふは怎なる面もちして出迎ふらん。室に入りて相対して見れば、形こそ旧に比ぶれば肥えて逞ましくなりたれ、依然たる快活の気象、我失行をもさまで意に介せざりきと見ゆ。別後の情を細叙するにも遑あらず、引かれて大臣に謁し、委托せられしは独逸語にて記せる文書の急を要するを飜訳せよとの事なり。余が文書を受領して大臣の室を出でし時、相沢は跡より来て余と午餐を共にせんといひぬ。
Ich bin aus dem Auto beim Eingang „Kaiserhof“ ausgestiegen. Ich habe den Portier um die Zimmernummer von meinem Sekretär, Herrn Aizawa, gebeten. Ich bin die Marmortreppe hinaufgegangen. Ich bin lange nicht auf so einer Treppe gegangen. Im Zimmer war ein Sofa mit einem Tuch. Ich habe vor einem Spiegel gestanden. Ich habe meinen Mantel ausgezogen und bin durch den Korridor gegangen. Vor der Tür habe ich kurz gezögert. Als Herr Aizawa früher mit mir an der Universität war, sagte er, dass ich ein guter Mensch bin. Wie würde Herr Aizawa heute über mich denken? Ich bin in das Zimmer gegangen und habe ihn gesehen. Sein Körper war jetzt dicker und stärker als früher, aber er war immer noch freundlich und schien meinen Fehler nicht so schlimm zu finden. Ohne über unsere Zeit nach der Trennung zu sprechen, hat er mich zum Minister gebracht. Der Minister hat mich gebeten, ein sehr wichtiges und dringendes Dokument, das auf Deutsch geschrieben ist, zu übersetzen. Als ich das Dokument genommen habe und aus dem Zimmer gegangen bin, kam Herr Aizawa hinter mir her und sagte: „Lasst uns zu Mittag essen!“
食事の席では、彼が多く質問し、私が多く答えた。彼の人生はおおむね順調だったが、私の身の上は困難が多く、波乱に富んでいたからである。私の心を開いて話した不幸な経験を聞いて、彼は何度も驚いたが、私を責めようとは全くしなかった。むしろ、他の平凡な学生たちをひどく非難した。しかし、私が話を終えたとき、彼は真顔になって私を諭すように言った。「この一件については、もともと持って生まれた心の弱さが原因だから、今さら言っても仕方がない。とはいえ、学識や才能がある君が、いつまでも一人の少女の愛情に囚われて、目的のない生活を続けるべきではない。」
「今、天方伯はただドイツ語を使う能力だけを求めていて君の個人的なことには関心はない。私も、伯爵が以前免職になった理由を知っているため、無理に彼の君に対する先入観を変えようとは思わない。伯爵に心の中で『えこひいきをする者だ』などと思われるのは、友人である君のためにもならないし、私自身にとっても損になるからだ。人に推薦してもらうためには、まずその能力を示すのが一番だ。能力を示して、伯爵の信用を得るべきだ。また、その少女との関係は、たとえ彼女に誠実な気持ちがあっても、たとえ愛情が深くなっていたとしても、君の才能を理解した上での恋ではない。それは、毎日の慣れという一種の惰性から生まれた付き合いなのだ。」
食卓にては彼多く問ひて、我多く答へき。彼が生路は概ね平滑なりしに、轗軻数奇なるは我身の上なりければなり。余が胸臆を開いて物語りし不幸なる閲歴を聞きて、かれは屡〻驚きしが、なか/\に余を譴めんとはせず、却りて他の凡庸なる諸生輩を罵りき。されど物語の畢りしとき、彼は色を正して諫むるやう、この一段のことは素と生れながらなる弱き心より出でしなれば、今更に言はんも甲斐なし。とはいへ、学識あり、才能あるものが、いつまでか一少女の情にかゝづらひて、目的なき生活をなすべき。今は天方伯も唯だ独逸語を利用せんの心のみなり。おのれも亦伯が当時の免官の理由を知れるが故に、強て其成心を動かさんとはせず、伯が心中にて曲庇者なりなんど思はれんは、朋友に利なく、おのれに損あればなり。人を薦むるは先づ其能を示すに若かず。これを示して伯の信用を求めよ。又彼少女との関係は、縦令彼に誠ありとも、縦令情交は深くなりぬとも、人材を知りてのこひにあらず、慣習といふ一種の惰性より生じたる交なり。意を決して断てと。是れその言のおほむねなりき。
Beim Essen stellte er viele Fragen, und ich antwortete viel. Denn sein Leben war größtenteils glatt verlaufen, während meines von vielen Schwierigkeiten und Turbulenzen geprägt war. Als er meine offen erzählten unglücklichen Erfahrungen hörte, war er zwar oft überrascht, doch er versuchte keineswegs, mich dafür zu tadeln. Im Gegenteil, er kritisierte die anderen gewöhnlichen Studenten scharf. Als ich jedoch meine Erzählung beendete, wurde er ernst und belehrte mich eindringlich: „Über diese Sache lässt sich nichts mehr sagen, da die Ursache von deiner angeborenen Herzensschwäche herrührt. Dennoch solltest du, als jemand mit Wissen und Talent, nicht weiterhin ein zielloses Leben führen, indem du ewig an der Liebe eines einzigen Mädchens festhältst. Derzeit verlangt Graf Amakata lediglich nach der Fähigkeit, Deutsch zu sprechen. Auch ich weiß, warum der Graf früher entlassen wurde, und will seine Vorurteile nicht gewaltsam ändern. Denn wenn der Graf innerlich denkt, ich sei ein Günstlingswahrer, wäre das weder für dich, meinen Freund, förderlich noch würde es mir selbst nützen. Um jemanden zu empfehlen, ist es am besten, zuerst dessen Können zu demonstrieren. Du solltest deine Fähigkeiten zeigen und das Vertrauen des Grafen gewinnen. Außerdem ist die Beziehung zu jenem Mädchen, selbst wenn ihre Gefühle aufrichtig sind und die Zuneigung tief geworden ist, keine Liebe, die dein Talent wirklich erkennt. Es ist lediglich ein Umgang, der aus einer Art Trägheit durch die tägliche Gewohnheit entstanden ist.
相沢が私に示した未来の道は、大きな海で舵を失った船が、遠くの山を見つけたようなものである。
しかし、その山はまだ霧の中にあり、いつたどり着くのか、いや、もし着いたとしても、私の心が本当に満足できるかどうかは分からない。貧しくても今の生活は楽しいものであり、捨てがたいのはエリスの愛である。
私は弱い心のため、はっきりと決めることができなかったが、しばらく友の言葉に従って、この恋を終わらせると約束した。
私は信念を失わないようにと思い、自分に反するものには反抗するが、友に対しては「いいえ」と言えないことが多いのである。
別れて外に出ると、風が顔を打った。
二重のガラス窓をしっかり閉め、大きなストーブに火が燃えていたホテルの食堂を出たので、薄いコートを通して午後四時の寒さが特に強く感じられた。
肌に鳥肌が立つとともに、私は心の中にも冷たいものを感じたのである。
大洋に舵を失ひしふな人が、遙なる山を望む如きは、相沢が余に示したる前途の方鍼なり。されどこの山は猶ほ重霧の間に在りて、いつ往きつかんも、否、果して往きつきぬとも、我中心に満足を与へんも定かならず。貧きが中にも楽しきは今の生活、棄て難きはエリスが愛。わが弱き心には思ひ定めんよしなかりしが、姑く友の言に従ひて、この情縁を断たんと約しき。余は守る所を失はじと思ひて、おのれに敵するものには抗抵すれども、友に対して否とはえ対へぬが常なり。
別れて出づれば風面を撲てり。二重の玻璃窓を緊しく鎖して、大いなる陶炉に火を焚きたる「ホテル」の食堂を出でしなれば、薄き外套を透る午後四時の寒さは殊さらに堪へ難く、膚粟立つと共に、余は心の中に一種の寒さを覚えき。
Aizawa zeigte mir einen Weg für meine Zukunft, der wie ein Schiff war, das auf dem großen Meer das Steuer verloren hat und in der Ferne einen Berg sieht. Aber dieser Berg liegt noch im Nebel, und ich weiß nicht, wann ich ihn erreichen werde. Ja, selbst wenn ich ihn erreiche, weiß ich nicht, ob mein Herz wirklich zufrieden sein wird. Auch wenn ich arm bin, ist mein jetziges Leben angenehm, und was ich nicht aufgeben kann, ist Ellis’ Liebe. Wegen meines schwachen Herzens konnte ich keine klare Entscheidung treffen, aber ich versprach, dem Rat meines Freundes zu folgen und diese Liebe zu beenden. Ich wollte meine Überzeugung nicht verlieren und widersetzte mich Dingen, die gegen mich waren, aber zu Freunden konnte ich oft kein „Nein“ sagen. Als ich mich trennte und hinausging, schlug mir der Wind ins Gesicht. Ich hatte die doppelten Glasfenster fest geschlossen und den Speisesaal des Hotels verlassen, in dem ein großer Ofen brannte. Deshalb fühlte sich die Kälte um vier Uhr nachmittags durch meinen dünnen Mantel besonders stark an.Gleichzeitig bekam ich Gänsehaut auf der Haut und spürte auch in meinem Herzen eine Art Kälte.
翻訳の仕事は一晩で終わった。それから私は「カイゼルホーフ」に行くことがだんだん多くなった。初めのうちは伯爵の話は用事のことだけだったが、しだいに彼は最近の故郷での出来事を話し、私の意見を聞くようになった。また、旅の途中での人々の失敗を話して、笑うこともあった。一か月ほどたったある日、伯爵は急に私に言った。
「私は明日ロシアに行くつもりである。君もいっしょに来るか。」私はここ数日、忙しい相沢に会っていなかったので、この質問はとても急で驚いた。
「どうしてお命に従わないことがあろうか。」と私は答えた。この答えは、よく考えて決めたものではなかった。私は信頼している人に突然質問されると、すぐに答えてしまうことがある。そのとき、答えの結果をよく考えずに「はい」と言ってしまうのだ。
そしてあとで、それが自分には難しいことだと気づいても、そのときの弱い気持ちを隠し、我慢して約束を守ろうとすることがよくあるのだ。
飜訳は一夜になし果てつ。「カイゼルホオフ」へ通ふことはこれより漸く繁くなりもて行く程に、初めは伯の言葉も用事のみなりしが、後には近比故郷にてありしことなどを挙げて余が意見を問ひ、折に触れては道中にて人々の失錯ありしことどもを告げて打笑ひ玉ひき。
一月ばかり過ぎて、或る日伯は突然われに向ひて、「余は明旦、魯西亜に向ひて出発すべし。随ひて来べきか、」と問ふ。余は数日間、かの公務に遑なき相沢を見ざりしかば、此問は不意に余を驚かしつ。「いかで命に従はざらむ。」余は我恥を表はさん。此答はいち早く決断して言ひしにあらず。余はおのれが信じて頼む心を生じたる人に、卒然ものを問はれたるときは、咄嗟の間、その答の範囲を善くも量らず、直ちにうべなふことあり。さてうべなひし上にて、その為し難きに心づきても、強て当時の心虚なりしを掩ひ隠し、耐忍してこれを実行すること屡々なり。
Die Übersetzung war in einer Nacht fertig. Danach begann ich, immer häufiger ins „Kaiserhof“ zu gehen. Am Anfang sprach der Graf nur über geschäftliche Dinge. Doch nach und nach erzählte er mir von Ereignissen in seiner Heimat und fragte nach meiner Meinung. Manchmal berichtete er auch über Fehler, die Menschen auf der Reise gemacht hatten, und lachte darüber. Etwa einen Monat später sagte der Graf plötzlich zu mir: „Ich werde morgen nach Russland reisen. Willst du mitkommen?“ Ich hatte Aizawa, der sehr beschäftigt war, seit einigen Tagen nicht gesehen, daher überraschte mich diese Frage sehr. Ich antwortete: „Wie könnte ich deinem Befehl nicht folgen?“ Diese Antwort kam jedoch nicht aus einer überlegten Entscheidung. Wenn mich jemand, dem ich vertraue, plötzlich etwas fragt, antworte ich manchmal sofort, ohne über die Folgen nachzudenken. Auch wenn ich später merke, dass es schwer für mich ist, versuche ich, mein damaliges schwaches Herz zu verstecken und das Versprochene trotzdem zu erfüllen.
この日、私は翻訳の給料をもらい、さらに旅費までいただいて家に帰った。
そして、翻訳の給料をエリスにあずけた。
これで、ロシアから帰ってくるまでのお金は足りるはずだ。エリスは医者に見せたところ、体の調子が悪いと言われた。
彼女は貧血の体質であり、何か月も気づかずにいたのである。彼女はダンスの仕事を長く休んでいたので、劇場から仕事をやめるように言われた。まだ一か月ほどしか休んでいないのに、こんなに厳しいのは理由があるのだろう。エリスは、私の旅立ちについてそれほど心配していないようであった。それは、私の本当の心を強く信じているからである。
此日は飜訳の代
に、旅費さへ添へて賜
はりしを持て帰りて、飜訳の代をばエリスに預けつ。これにて魯西亜より帰り来んまでの費
をば支へつべし。彼は医者に見せしに常ならぬ身なりといふ。貧血の性
なりしゆゑ、幾月か心づかでありけん。座頭よりは休むことのあまりに久しければ籍を除きぬと言ひおこせつ。まだ一月ばかりなるに、かく厳しきは故あればなるべし。旅立の事にはいたく心を悩ますとも見えず。偽りなき我心を厚く信じたれば。
An diesem Tag bekam ich meinen Lohn für die Übersetzung und sogar noch Reisegeld dazu, und ich ging nach Hause. Ich gab das Geld für die Übersetzung Ellis zur Aufbewahrung. Damit sollte das Geld bis zu meiner Rückkehr aus Russland ausreichen. Ellis ging zum Arzt, und er sagte, dass es ihr körperlich nicht gut gehe. Sie leidet unter Blutarmut und hatte es mehrere Monate lang nicht bemerkt. Weil sie lange mit dem Tanzen ausgesetzt hatte, sagte das Theater, dass sie aufhören solle. Obwohl erst ungefähr ein Monat vergangen war, war diese Strenge wohl aus einem bestimmten Grund. Ellis schien sich nicht sehr um meine Reise zu sorgen. Denn sie glaubte fest an mein aufrichtiges Herz.
この旅は電車で行くので、そんなに遠くない。だから、あまり準備はなかった。
黒い礼服を借りて、ロシアの貴族について書いてある本や、2〜3冊の辞書を、小さなカバンに入れただけであった。最近、私はとても心細かった。だから、出かけたあとにエリスが1人で家に残るエリスを見るのは、つらいと思ったが、かといって駅でエリスに泣かれるのも、つらくなると思ったので、次の朝早く、エリスを母親のところへ行かせた。私は旅行の準備をして、家の戸を閉め、家の入口に住んでいる靴屋の主人に鍵をあずけて出かけた。
鉄路にては遠くもあらぬ旅なれば、用意とてもなし。身に合せて借りたる黒き礼服、新に買求めたるゴタ板の魯廷
の貴族譜、二三種の辞書などを、小「カバン」に入れたるのみ。流石に心細きことのみ多きこの程なれば、出で行く跡に残らんも物憂かるべく、又停車場にて涙こぼしなどしたらんには影護
かるべければとて、翌朝早くエリスをば母につけて知る人がり出
しやりつ。余は旅装整へて戸を鎖し、鍵をば入口に住む靴屋の主人に預けて出でぬ。
Die Reise war nicht besonders weit, weil ich mit dem Zug fahren würde. Deshalb musste ich nicht viel vorbereiten. Ich hatte mir einen schwarzen Frack ausgeliehen und einige Bücher über den russischen Adel sowie zwei oder drei Wörterbücher in eine kleine Tasche gepackt. In letzter Zeit fühlte ich mich sehr unsicher und einsam. Deshalb dachte ich, es wäre für mich schwer, wenn Ellis allein zu Hause bleiben würde, nachdem ich abgereist war. Außerdem dachte ich, dass es mir wehtun würde, wenn sie am Bahnhof weinen müsste. Darum ließ ich sie am frühen Morgen zu ihrer Mutter gehen. Ich bereitete mein Reisegepäck vor, schloss die Haustür ab und gab den Schlüssel dem Schuster, der im Eingang des Hauses wohnte, bevor ich aufbrach.
ロシア行きについて、何を書くべきだろうか。私の通訳としての仕事は、突然私を引っ張って、まるで高い雲の上に落としたようだった。私は大臣の一行に加わり、ペテルブルクにいた。そのとき私を取り囲んでいたのは、パリのぜいたくな雰囲気を氷と雪の中にうつしたような王の宮殿のようすだった。たくさんの黄色いろうそくがともされ、たくさんの勲章や肩章(軍服のかた飾り)が光っていた。彫刻の細工をこらした暖炉の火がゆらめき、寒さを忘れさせた。宮女たちが扇を動かす光もきらめいていた。その中で、フランス語をいちばん上手に話したのは私であった。だから、客と主人の間で話をまとめる仕事の多くも、私がした。
魯国行につきては、何事をか叙すべき。わが舌人
たる任務
は忽地
に余を拉
し去りて、青雲の上に堕
したり。余が大臣の一行に随ひて、ペエテルブルクに在りし間に余を囲繞
せしは、巴里絶頂の驕奢
を、氷雪の裡
に移したる王城の粧飾
、故
らに黄蝋
の燭
を幾つ共なく点
したるに、幾星の勲章、幾枝の「エポレツト」が映射する光、彫鏤
の工
を尽したる「カミン」の火に寒さを忘れて使ふ宮女の扇の閃きなどにて、この間仏蘭西語を最も円滑に使ふものはわれなるがゆゑに、賓主の間に周旋して事を弁ずるものもまた多くは余なりき。
Ich überlege, was ich über meine Reise nach Russland schreiben soll. Meine Arbeit als Dolmetscher hat mich plötzlich in eine neue, sehr hohe Lage gebracht, als wäre ich auf eine Wolke hinaufgeworfen worden. Ich gehörte zur Delegation des Ministers und war in Sankt Petersburg. Um mich herum war der Palast des Königs, der den Luxus von Paris in das Eis und den Schnee Russlands versetzt zu haben schien. Viele gelbe Kerzen waren angezündet, und viele Orden und Epauletten glänzten im Licht. Das Feuer im kunstvoll geschnitzten Kamin flackerte und ließ uns die Kälte vergessen. Die Fächer der Hofdamen blitzten, während sie sich bewegten. Unter allen war ich derjenige, der am besten Französisch sprach. Deshalb übernahm ich oft die Aufgabe, zwischen Gastgeber und Gästen zu vermitteln.
この期間、私はエリスを忘れることができなかった。いや、彼女が毎日のように手紙を送ってきたので、忘れられるはずがなかった。私が出発した日は、夜一人で灯りをつけて一人で考え事をしたりしてしまうのが、いつもにもましてつらかったので、知人の家で夜まで語り合って、疲れるのを待って家に帰り、すぐに眠った。翌朝目が覚めたときには、一人取り残されたのは今も夢ではなかったのだと思った。起きようとしたときの心細さといったら、生活に困って今日の食べ物がなかったときでさえ感じなかったほどのものだった。これが彼女の一通目の手紙のおおよその内容だ。
この間余はエリスを忘れざりき、否、彼は日毎に書
を寄せしかばえ忘れざりき。余が立ちし日には、いつになく独りにて燈火に向はん事の心憂さに、知る人の許
にて夜に入るまでもの語りし、疲るゝを待ちて家に還り、直ちにいねつ。次の朝
目醒めし時は、猶独り跡に残りしことを夢にはあらずやと思ひぬ。起き出でし時の心細さ、かゝる思ひをば、生計
に苦みて、けふの日の食なかりし折にもせざりき。これ彼が第一の書の略
なり。
Während dieser Zeit konnte ich Ellis nicht vergessen. Nein, es war unmöglich, sie zu vergessen, weil sie mir fast jeden Tag Briefe schrieb. Am Tag meiner Abreise war es ihr besonders schwer, in der Nacht allein bei Licht zu sitzen und nachzudenken. Deshalb ging sie zu einer Bekannten, sprach mit ihr bis in die Nacht und kehrte erst heim, als sie müde wurde, um sofort einzuschlafen. Als sie am nächsten Morgen erwachte, dachte sie, dass das Alleinsein noch immer kein Traum sei. Als sie aufstehen wollte, fühlte sie eine Einsamkeit, wie sie sie selbst dann nicht gespürt hatte, als sie einmal kein Geld und kein Essen für den Tag hatte.
Dies ist der ungefähre Inhalt ihres ersten Briefes.
しばらくして届いた手紙は、とても感情がこもっているようだった。文の最初は「いいえ」という言葉で始まっていた。「いいえ、私は今になって、あなたを思う心の深さを知りました。あなたには故郷に頼れる家族がいないと言っていたから、この地で良い暮らしの方法が見つかるなら、あなたがここに残らない理由はないでしょう。もし私の愛であなたを引きとめられるなら、私はそうしたいと思っています。しかしそれが無理で、あなたが東の国へ帰ることになるなら、親と一緒に行くと言ってみるのは簡単ですが、そんなに大きな旅の費用をどこから手に入れればよいでしょう。どんな仕事をしてでも私はこの地に残り、あなたが立派になって世に出る日を待とうと思っています。けれど、あなたが短い旅に出たあの日から二十日ほどたった今、別れの思いは日ごとに強くなっています。別れることは一瞬の苦しみだと思っていましたが、それは間違いでした。自分の身が不安定であることがようやくはっきりわかってきた今、たとえどんなことがあっても、私を決して見捨てないでください。母とはひどく言い争いました。でも、私が前よりも真剣に考えて決めたことを見て、母はあきらめたようです。あなたが東へ行くことになったら、シュテッティンの近くの農家に遠い親戚がいるので、そこに身を寄せようと思います。あなたが前に書いていたように、大臣に重く用いられるようになれば、あなたが国に帰る旅費のことはどうにかなるでしょう。今はただ、あなたがベルリンへ帰ってくる日をひたすら待つばかりです。」
又程経てのふみは頗る思ひせまりて書きたる如くなりき。文をば否といふ字にて起したり。否、君を思ふ心の深き底をば今ぞ知りぬる。君は故里に頼もしき族なしとのたまへば、此地に善き世渡のたつきあらば、留り玉はぬことやはある。又我愛もて繋ぎ留めでは止まじ。それもはで東に還り玉はんとならば、親と共に往かんは易けれど、か程に多き路用を何処よりか得ん。怎なる業をなしても此地に留りて、君が世に出で玉はん日をこそ待ためと常には思ひしが、暫しの旅とて立出で玉ひしより此二十日ばかり、別離の思は日にけに茂りゆくのみ。袂を分つはたゞ一瞬の苦艱なりと思ひしは迷なりけり。我身の常ならぬが漸くにしるくなれる、それさへあるに、縦令いかなることありとも、我をば努な棄て玉ひそ。母とはいたく争ひぬ。されど我身の過ぎし頃には似で思ひ定めたるを見て心折れぬ。わが東に往かん日には、ステツチンわたりの農家に、遠き縁者あるに、身を寄せんとぞいふなる。書きおくり玉ひし如く、大臣の君に重く用ゐられ玉はゞ、我路用の金は兎も角もなりなん。今は只管君がベルリンにかへり玉はん日を待つのみ。
Nach einiger Zeit erhielt ich einen Brief, der mir sehr gefühlvoll erschien. Der Brief begann mit dem Wort „Nein“. „Nein, erst jetzt habe ich erkannt, wie tief meine Gefühle für dich wirklich sind. Du hast mir gesagt, dass du in deiner Heimat keine Familie hast, auf die du dich verlassen kannst. Deshalb denke ich, dass du hierbleiben könntest, wenn du in diesem Land eine gute Lebensmöglichkeit findest. Wenn ich dich mit meiner Liebe halten könnte, würde ich es tun. Aber wenn das nicht möglich ist und du in den Osten zurückkehren musst, wäre es zwar leicht, mit meinen Eltern zu gehen, doch woher soll ich das viele Geld für die Reise bekommen? Ich möchte, egal welche Arbeit ich tun muss, hierbleiben und auf den Tag warten, an dem du erfolgreich wirst und in der Gesellschaft anerkannt bist. Seit dem Tag, an dem du zu einer kurzen Reise aufgebrochen bist, sind etwa zwanzig Tage vergangen, und mein Gefühl der Trennung wird von Tag zu Tag stärker. Ich dachte, Abschied zu nehmen sei nur ein kurzer Schmerz, aber ich habe mich geirrt. Jetzt erkenne ich klar, dass mein eigenes Leben unsicher ist. Darum bitte ich dich, mich niemals zu verlassen, egal was geschieht. Ich habe mich heftig mit meiner Mutter gestritten. Aber als sie sah, dass ich diesmal wirklich entschieden bin, hat sie aufgegeben. Wenn ich in den Osten gehe, werde ich bei einer fernen Verwandten auf einem Bauernhof in der Nähe von Stettin wohnen. Wie du geschrieben hast, wenn du vom Minister stark gebraucht wirst, dann wird sich das mit dem Reisegeld sicher irgendwie lösen. Jetzt warte ich nur noch darauf, dass du nach Berlin zurückkehrst.“
ああ、私はこの手紙を見て、初めて自分の立場をはっきり知ることができた。
恥ずかしいのは、自分の鈍い心である。
私はこれまで、自分の進む道や他の人のことについても、きちんと決められると自信を持っていた。しかし、その決断はうまくいっているときだけで、つらいときにはできなかったのである。人との関係をよく考えようとすると、私が信じていた心の中の鏡は曇ってしまった。
嗚呼、余は此書を見て始めて我地位を明視し得たり。恥かしきはわが鈍
き心なり。余は我身一つの進退につきても、また我身に係らぬ他人
の事につきても、決断ありと自ら心に誇りしが、此決断は順境にのみありて、逆境にはあらず。我と人との関係を照さんとするときは、頼みし胸中の鏡は曇りたり。
Ach, erst als ich diesen Brief las, konnte ich meine eigene Lage klar erkennen. Beschämend ist mein träges Herz. Ich war bisher stolz darauf, sowohl über meine eigenen Entscheidungen als auch über die Angelegenheiten anderer Menschen klar urteilen zu können. Doch diese Entschlossenheit zeigte sich nur in guten Zeiten, nicht in schwierigen Momenten. Wenn ich versuche, meine Beziehung zu anderen zu verstehen, wird der Spiegel meines Herzens, auf den ich vertraut habe, trüb.
大臣はもう私に親切にしてくださるようになった。しかし、私は目の前にある、自分の仕事のことしか考えられなかった。私は、今の仕事に未来の希望が持てるかどうか、それは神だけが知ることで、自分にはまったく想像できなかった。しかし、今になってやっと、大臣が日本での仕事を与えてくれそうな状況なのだと気付いた。そして、自分の心がまだ冷静にこの状況を見ているのかどうかは分からなかった。最初に仕事を紹介してもらったときは、大臣の私への信用は頼りなかったが、今は信頼を得ることができたと思う。相沢は最近の会話で、「日本に帰ったあともこうしていられたら…」と言うようになった。つまり、大臣は相沢にそういうことをすでに言っていて、人事の問題で私にはまだはっきり伝えられていないないのだろう。今思えば、私が簡単に相沢にエリスと別れると言ったことを、相沢は大臣に告げたのだろうと思う。
大臣は既に我に厚し。されどわが近眼は唯だおのれが尽したる職分をのみ見き。余はこれに未来の望を繋ぐことには、神も知るらむ、絶えて想到らざりき。されど今こゝに心づきて、我心は猶ほ冷然たりし歟。先に友の勧めしときは、大臣の信用は屋上の禽の如くなりしが、今は稍〻これを得たるかと思はるゝに、相沢がこの頃の言葉の端に、本国に帰りて後も倶にかくてあらば云々しか〻といひしは、大臣のかく宣ひしを、友ながらも公事なれば明には告げざりし歟。今更おもへば、余が軽卒にも彼に向ひてエリスとの関係を絶たんといひしを、早く大臣に告げやしけん。
Der Minister war mir bereits freundlich gesinnt. Doch meine Kurzsichtigkeit ließ mich nur die Arbeit sehen, die ich mache. Ob ich in meiner jetzigen Arbeit Hoffnung für die Zukunft finden könnte, wusste nur Gott, und ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen. Erst jetzt wurde mir allmählich klar, dass der Minister mir in Japan wahrscheinlich Arbeit geben würde. Und ich wusste nicht, ob mein Herz diese Situation noch ruhig betrachten konnte. Als mir die Arbeit zum ersten Mal vermittelt wurde, war das Vertrauen des Ministers in mich gering, aber jetzt glaubte ich, sein Vertrauen gewonnen zu haben. Aizawa äußerte in letzter Zeit oft: „Wenn ich nach Japan zurückkehre, könnten wir weiterhin so zusammen bleiben…“ Das bedeutet, dass der Minister dies bereits Aizawa gesagt hat, aber wegen personaler Angelegenheiten mir gegenüber noch nicht klar ausgedrückt werden konnte. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, hat Aizawa wahrscheinlich dem Minister erzählt, dass ich leichtfertig gesagt hatte, mich von Ellis zu trennen.
ああ、ドイツに来たばかりのころ、私は自分の本当の力を理解したと思い、もう機械のような人間にはならないと誓った。
しかしそれは、足を縛られた鳥が、少しだけ羽を動かして自由を得たと勘違いして喜んでいるようなものだった。
私の足を縛る糸を解くことはできない。
以前その糸を操っていたのは、私の日本の省の上司であったが、今はその糸が、ああ悲しいことに、天方伯の手の中にある。
私が大臣たちといっしょにベルリンに帰ったのは、ちょうど新年の朝であった。
駅で別れを告げ、私は自分の家に向かって馬車を走らせた。
この国では、大晦日は眠らず、元日の朝に眠る習慣があるので、町の家々はとても静かであった。
寒さは厳しく、道の雪は角ばった氷のかけらになって、晴れた日の光にきらきらと輝いていた。
馬車がクロステル通りに曲がり、家の前に止まった。
そのとき、窓を開ける音がしたが、馬車の中からは誰か見えなかった。
私は馬車の運転手にカバンを持たせて階段を登ろうとしたとき、エリスが階段を駆け下りてくるのに出会った。
彼女は声を上げて私の首に抱きついた。
それを見た運転手は驚いた顔をして、ひげの中で何かをつぶやいたが、私には聞こえなかった。
「よく帰ってきてくれました。
もしあなたが帰ってこなかったら、私は生きてはいられなかったでしょう。」
嗚呼、独逸に来し初に、自ら我本領を悟りきと思ひて、また器械的人物とはならじと誓ひしが、こは足を縛して放たれし鳥の暫し羽を動かして自由を得たりと誇りしにはあらずや。足の糸は解くに由なし。曩
にこれを繰
つりしは、我
某
省の官長にて、今はこの糸、あなあはれ、天方伯の手中に在り。余が大臣の一行と倶にベルリンに帰りしは、恰
も是れ新年の旦
なりき。停車場に別を告げて、我家をさして車を駆
りつ。こゝにては今も除夜に眠らず、元旦に眠るが習なれば、万戸寂然たり。寒さは強く、路上の雪は稜角ある氷片となりて、晴れたる日に映じ、きら/\と輝けり。車はクロステル街に曲りて、家の入口に駐
まりぬ。この時窓を開く音せしが、車よりは見えず。馭丁
に「カバン」持たせて梯を登らんとする程に、エリスの梯を駈け下るに逢ひぬ。彼が一声叫びて我頸
を抱きしを見て馭丁は呆れたる面もちにて、何やらむ髭
の内にて云ひしが聞えず。「善くぞ帰り来玉ひし。帰り来玉はずば我命は絶えなんを。」
Als ich gerade nach Deutschland gekommen war, dachte ich, ich hätte endlich meine wahre Begabung erkannt und schwor, kein mechanischer Mensch mehr zu werden. Aber das war, als hätte ein gefesselter Vogel ein wenig mit den Flügeln geschlagen und geglaubt, er sei frei geworden. Die Fäden, die meine Füße binden, kann ich nicht lösen. Früher hielt mein Vorgesetzter im Ministerium in Japan diese Fäden in der Hand, aber jetzt, ach, sind sie in den Händen des Grafen Amakusa. Ich kehrte zusammen mit dem Minister und seinen Begleitern nach Berlin zurück, und es war gerade Neujahrsmorgen. Nachdem ich mich am Bahnhof verabschiedet hatte, fuhr ich mit der Kutsche zu meinem Haus. In diesem Land schläft man in der Neujahrsnacht nicht, sondern erst am Morgen des ersten Tages, daher war die Stadt ganz still. Es war sehr kalt, und der Schnee auf der Straße war zu eckigen Eisstücken geworden, die im Sonnenlicht funkelten. Die Kutsche bog in die Klosterstraße ein und hielt vor meinem Haus. In diesem Moment hörte ich, wie ein Fenster geöffnet wurde, aber aus der Kutsche konnte ich niemanden sehen. Ich ließ den Kutscher meinen Koffer tragen und wollte gerade die Treppe hinaufsteigen, als mir Ellis entgegengelaufen kam. Sie rief laut und schlang ihre Arme um meinen Hals. Der Kutscher sah überrascht aus und murmelte etwas in seinem Bart, aber ich konnte es nicht verstehen. „Ich bin so froh, dass du zurückgekommen bist. Wenn du nicht zurückgekehrt wärst, hätte ich nicht mehr leben können.“
私の心はこの時まで決まっていなかった。
ふるさとを思う気持ちと、出世を望む気持ちがあり、ときどきそのために愛の気持ちを抑えようとした。しかし、ちょうどこの一瞬、ためらいや迷いの思いが消えて、私は彼女を抱いた。彼女の頭は私の肩に寄りかかり、喜びの涙がぽろぽろと肩の上に落ちた。そのとき、馬車の運転手が「荷物はいくつ持っていくのですか」と、まるで太鼓のような大きな声で叫び、すばやく階段を登って上に立った。戸の外で出迎えたエリスの母に、私は運転手へのお礼として銀貨を渡し、「ねぎらってやってください」と言った。私はエリスに手を引かれて、急いで部屋に入った。そして一目見て驚いた。机の上には、白い木綿や白いレースが高く積み上げられていた。
我心はこの時までも定まらず、故郷を憶ふ念と栄達を求むる心とは、時として愛情を圧せんとせしが、唯だ此一刹那、低徊踟蹰の思は去りて、余は彼を抱き、彼の頭は我肩に倚りて、彼が喜びの涙ははら/\と肩の上に落ちぬ。
「幾階か持ちて行くべき。」と鑼の如く叫びし馭丁は、いち早く登りて梯の上に立てり。
戸の外に出迎へしエリスが母に、馭丁を労ひ玉へと銀貨をわたして、余は手を取りて引くエリスに伴はれ、急ぎて室に入りぬ。一瞥して余は驚きぬ、机の上には白き木綿、白き「レエス」などを堆く積み上げたれば。
Mein Herz war bis zu diesem Moment noch nicht entschieden. Ich dachte oft an meine Heimat und wünschte mir beruflichen Erfolg. Manchmal versuchte ich deshalb, meine Liebe zu unterdrücken. Aber in diesem einen Augenblick verschwanden alle Zweifel und jedes Zögern. Ich nahm sie in meine Arme, und ihr Kopf lehnte an meiner Schulter. Ihre Tränen der Freude fielen leise auf meine Schulter. In diesem Moment rief der Kutscher laut wie eine Trommel: „Wie viele Gepäckstücke sollen mitgenommen werden?“ Schnell stieg er die Treppe hinauf und stand oben. Draußen an der Tür wartete Ellis’ Mutter, und ich gab ihr eine Silbermünze als Dank für den Kutscher. Ich sagte: „Bitte belohnen Sie ihn dafür.“ Ellis nahm mich an der Hand, und wir gingen eilig in das Zimmer. Ich sah mich um und war überrascht. Auf dem Tisch lagen viele weiße Baumwollstoffe und Spitzen, die hoch aufeinander gestapelt waren.
エリスはほほえみながら、それらを指さして言った。「どう思いますか。この心づもりを見てください」と言い、白い木綿の切れを一つ手に取った。それは赤んぼうのための布であった。「私のうれしい気持ちを想像してください。生まれてくる子どもは、あなたに似て黒い目を持つでしょう。この黒い目…ああ、私は夢の中であなたの黒い目ばかり見ていたのです。生まれた日には、あなたは正しい心で、子どもに悪い名前をつけたりしないでしょう。」彼女は頭を下げた。「子どもが小さいとき、あなたは笑うでしょう。そして、子どもが教会に入る日が来たら、どれほどうれしいことでしょう。」彼女が顔を上げたとき、目には涙がいっぱいにたまっていた。
エリスは打笑
みつゝこれを指
して、「何とか見玉ふ、この心がまへを。」といひつゝ一つの木綿ぎれを取上ぐるを見れば襁褓
なりき。「わが心の楽しさを思ひ玉へ。産れん子は君に似て黒き瞳子
をや持ちたらん。この瞳子。嗚呼、夢にのみ見しは君が黒き瞳子なり。産れたらん日には君が正しき心にて、よもあだし名をばなのらせ玉はじ。」彼は頭を垂れたり。「穉
しと笑ひ玉はんが、寺に入らん日はいかに嬉しからまし。」見上げたる目には涙満ちたり。
Elis lächelte und zeigte auf die Gegenstände. Sie sagte: „Was meinst du? Sieh dir bitte diese Vorbereitung an.“ Dann nahm sie ein Stück weißes Baumwolltuch in die Hand. Es war ein Tuch für ein neugeborenes Kind. „Stell dir vor, wie groß meine Freude ist.“ „Das Kind, das geboren wird, wird dir ähnlich sehen und dunkle Augen haben.“ „Diese Augen… ach, ich habe in meinen Träumen immer nur deine dunklen Augen gesehen.“ „Wenn das Kind zur Welt kommt, wirst du es mit reinem Herzen betrachten und ihm sicher keinen schlechten Namen geben.“ Sie senkte den Kopf. „Wenn das Kind noch klein ist, wirst du freundlich über ihn lachen.“ „Und wenn der Tag kommt, an dem es in die Kirche aufgenommen wird, wirst du sehr glücklich sein.“ Als sie wieder aufsah, standen Tränen in ihren Augen.
a
二三日の間は大臣をも、たびの疲れやおはさんとて敢
て訪
らはず、家にのみ籠り居
しが、或る日の夕暮使して招かれぬ。往きて見れば待遇殊にめでたく、魯西亜行の労を問ひ慰めて後、われと共に東にかへる心なきか、君が学問こそわが測り知る所ならね、語学のみにて世の用には足りなむ、滞留の余りに久しければ、様々の係累もやあらんと、相沢に問ひしに、さることなしと聞きて落居
たりと宣ふ。其気色辞
むべくもあらず。あなやと思ひしが、流石に相沢の言
を偽なりともいひ難きに、若しこの手にしも縋
らずば、本国をも失ひ、名誉を挽
きかへさん道をも絶ち、身はこの広漠たる欧洲大都の人の海に葬られんかと思ふ念、心頭を衝
いて起れり。嗚呼、何等の特操なき心ぞ、「承
はり侍
り」と応
へたるは。
b
a
黒がねの額
はありとも、帰りてエリスに何とかいはん。「ホテル」を出でしときの我心の錯乱は、譬
へんに物なかりき。余は道の東西をも分かず、思に沈みて行く程に、往きあふ馬車の馭丁に幾度か叱
せられ、驚きて飛びのきつ。暫くしてふとあたりを見れば、獣苑の傍
に出でたり。倒るゝ如くに路の辺
の榻
に倚りて、灼くが如く熱し、椎
にて打たるゝ如く響く頭
を榻背
に持たせ、死したる如きさまにて幾時をか過しけん。劇しき寒さ骨に徹すと覚えて醒めし時は、夜に入りて雪は繁く降り、帽の庇
、外套の肩には一寸許
も積りたりき。
b
a
最早十一時をや過ぎけん、モハビツト、カルヽ街通ひの鉄道馬車の軌道も雪に埋もれ、ブランデンブルゲル門の畔の瓦斯燈は寂しき光を放ちたり。立ち上らんとするに足の凍えたれば、両手にて擦りて、漸やく歩み得る程にはなりぬ。
足の運びの捗らねば、クロステル街まで来しときは、半夜をや過ぎたりけん。こゝ迄来し道をばいかに歩みしか知らず。一月上旬の夜なれば、ウンテル、デン、リンデンの酒家、茶店は猶ほ人の出入盛りにて賑はしかりしならめど、ふつに覚えず。我脳中には唯

我は免すべからぬ罪人なりと思ふ心のみ満ち/\たりき。
b
a
四階の屋根裏には、エリスはまだ寝ねずと覚ぼしく、烱然たる一星の火、暗き空にすかせば、明かに見ゆるが、降りしきる鷺の如き雪片に、乍ち掩はれ、乍ちまた顕れて、風に弄ばるゝに似たり。戸口に入りしより疲を覚えて、身の節の痛み堪へ難ければ、這ふ如くに梯を登りつ。庖厨を過ぎ、室の戸を開きて入りしに、机に倚りて襁褓縫ひたりしエリスは振り返へりて、「あ」と叫びぬ。「いかにかし玉ひし。おん身の姿は。」
驚きしも宜なりけり、蒼然として死人に等しき我面色、帽をばいつの間にか失ひ、髪は蓬ろと乱れて、幾度か道にて跌き倒れしことなれば、衣は泥まじりの雪に

れ、処々は裂けたれば。
b
a
余は答へんとすれど声出でず、膝の頻りに戦かれて立つに堪へねば、椅子を握まんとせしまでは覚えしが、その儘に地に倒れぬ。
人事を知る程になりしは数週の後なりき。熱劇しくて譫語のみ言ひしを、エリスが慇にみとる程に、或日相沢は尋ね来て、余がかれに隠したる顛末を審らに知りて、大臣には病の事のみ告げ、よきやうに繕ひ置きしなり。余は始めて、病牀に侍するエリスを見て、その変りたる姿に驚きぬ。彼はこの数週の内にいたく痩せて、血走りし目は窪み、灰色の頬は落ちたり。相沢の助にて日々の生計には窮せざりしが、此恩人は彼を精神的に殺しゝなり。
b
a
後に聞けば彼は相沢に逢ひしとき、余が相沢に与へし約束を聞き、またかの夕べ大臣に聞え上げし一諾を知り、俄
に座より躍り上がり、面色さながら土の如く、「我豊太郎ぬし、かくまでに我をば欺き玉ひしか」と叫び、その場に僵
れぬ。相沢は母を呼びて共に扶
けて床に臥させしに、暫くして醒めしときは、目は直視したるまゝにて傍の人をも見知らず、我名を呼びていたく罵り、髪をむしり、蒲団
を噛みなどし、また遽
に心づきたる様にて物を探り討
めたり。母の取りて与ふるものをば悉
く抛
ちしが、机の上なりし襁褓を与へたるとき、探りみて顔に押しあて、涙を流して泣きぬ。
b
a
これよりは騒ぐことはなけれど、精神の作用は殆
全く廃して、その痴
なること赤児の如くなり。医に見せしに、過劇なる心労にて急に起りし「パラノイア」といふ病
なれば、治癒の見込なしといふ。ダルドルフの癲狂院
に入れむとせしに、泣き叫びて聴かず、後にはかの襁褓一つを身につけて、幾度か出しては見、見ては欷歔
す。余が病牀をば離れねど、これさへ心ありてにはあらずと見ゆ。たゞをり/\思ひ出したるやうに「薬を、薬を」といふのみ。
b
a
余が病は全く癒えぬ。エリスが生ける屍を抱きて千行の涙を濺ぎしは幾度ぞ。大臣に随ひて帰東の途に上ぼりしときは、相沢と議りてエリスが母に微なる生計を営むに足るほどの資本を与へ、あはれなる狂女の胎内に遺しゝ子の生れむをりの事をも頼みおきぬ。
嗚呼、相沢謙吉が如き良友は世にまた得がたかるべし。されど我脳裡に一点の彼を憎むこゝろ今日までも残れりけり。
(明治二十三年一月)
b
a
b
a
b
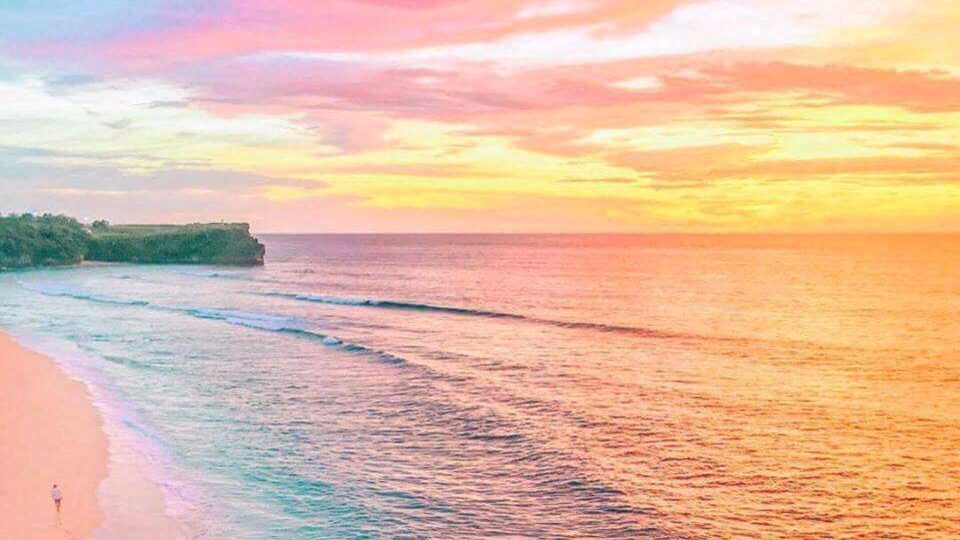


コメント